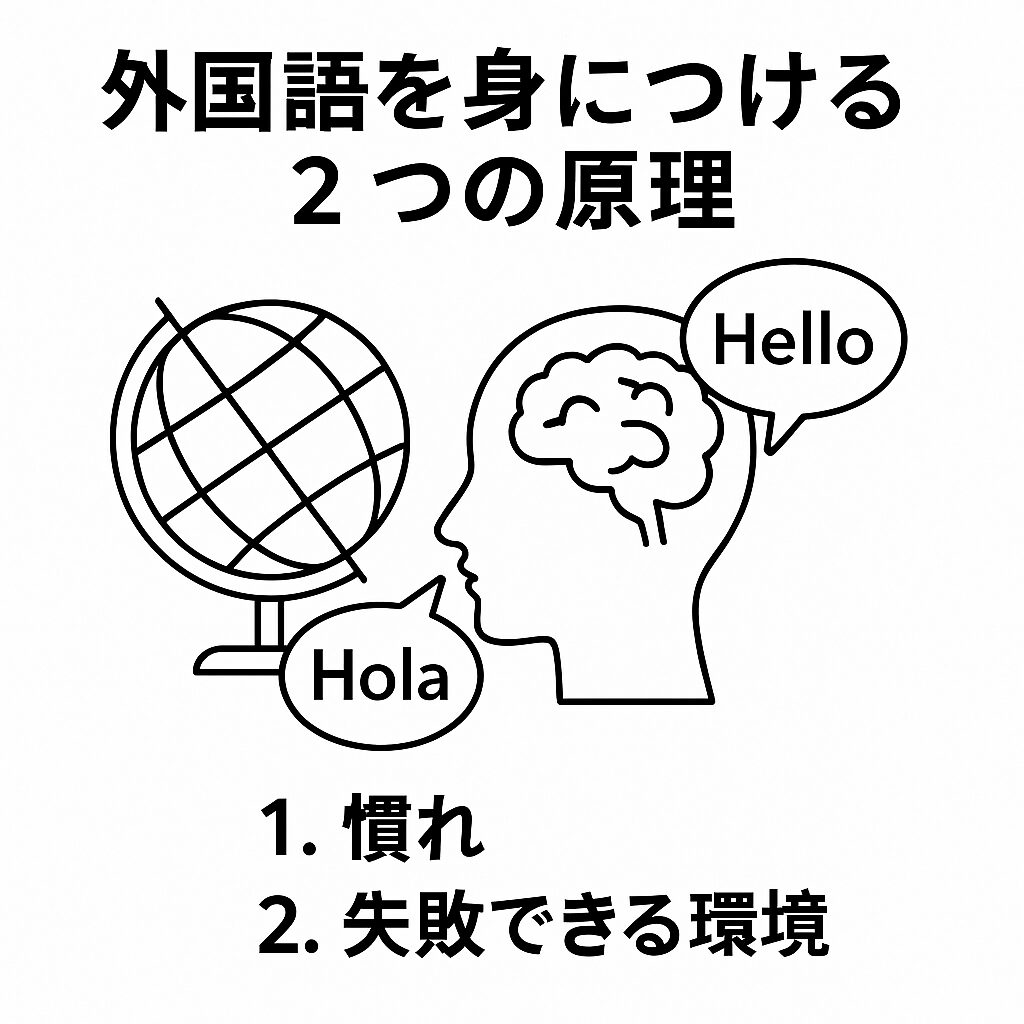Contents
はじめに
日本は、文明も文化も日本語で高度に構築された国である。
そのため、外国語を使わなくても社会生活が完結してしまう。
これは世界的に見ても珍しいことであり、英語を操れなくても困らない国は、実はそう多くない。
しかし、「外国語を理解できるようになりたい」という願望そのものは、人間としてきわめて自然な欲求だ。
異なる言語を通して世界を見てみたい、違う文化の人と直接話したい──その思いは知的好奇心の表れにほかならない。
では、日本人が英語を苦手とするのはなぜか。
そして、どうすれば本当に“使える外国語”を身につけられるのか。
40年以上にわたり英語に触れ続けてきた『理屈コネ太郎』の経験をもとに、その答えを整理してみたい。
第1章 日本人が英語を苦手とする2つの理由
理由その1:必要性が低い
日本国内では、英語を操る必要性が極端に低い。
日本語だけで生活が完結する環境では、外国語を使う動機そのものが生まれにくい。
経済的にも文化的にも自立した国であり、学術・ニュース・エンタメの多くが翻訳を通じて日本語化されている。
言い換えれば、「英語を使わなくても十分に豊かな生活ができてしまう」のである。
人口が少ない国や、外国語を使わざるを得ない国では、英語は生活の必需品だ。
だが日本では、英語を使わないまま生涯を終えることも珍しくない。
理由その2:英語教育が“採点の道具”になった
もうひとつの理由は、日本の英語教育が長らく“学生選抜の道具”として機能してきたことだ。
正確な文法・語彙・訳を重視する「減点方式」によって、英語が“試験科目”になってしまった。
その結果、英語を「使うための言語」ではなく、「点を取るための知識」として扱う風潮が根付いた。
外国に暮らしたこともない教師が、クラス全員に単語の唱和を強制し、発音を採点していた時代もあった。
冷静に考えれば、あれは教育ではなく、統制である。
第2章 言語習得の本質は「慣れ」にある
外国語に限らず、あらゆる知識や技能には共通する要点がある。
それは――
慣れること
間違えても大丈夫な環境で試すこと
の二つである。
理解する前に慣れる。
これが私の40年の経験から得た確信だ。
「理解してから使う」ではなく、「慣れてから理解する」――
この順序を誤ると、どれだけ勉強しても使えるようにはならない。
言葉に対する違和感が減るほど、吸収は速くなる。
「あ、これ見たことある」「聞いたことある」という単語や構文が増えれば、
やがて“意味がわかる前に使える”段階に入っていく。
第3章 800文で世界が変わる
よく「800文覚えれば英語は喋れる」と言われる。
市販の書籍にもそうしたタイトルが見られるが、これは決して誇張ではない。
私自身、40年間英語に触れ続けてきてほぼ断言できる。
日常会話レベルの英語は驚くほどパターン化されている。
そして、この“約800の文パターン”を身体の中に入れておくだけで、その後の学習は劇的にスムースになる。
ただし、この「800文」とは、教科書の例文のことではない。
自分が興味をもつ分野――車でも釣りでも政治でも映画でも――で実際に使われている生きた表現である。
「自分もこれ言いたいな」と思った文を一つずつ拾っていけば、それが“自分専用の800文”になる。
それこそが「慣れの地図」だ。
第4章 “間違えても平気”な環境に身を置く
「慣れ」の前提にあるのが、“間違いを恐れずに試行できる環境”だ。
被採点者の立場にいる限り、学習は点取りゲームに陥る。
評価されることを前提とした学びは、創造的な試行を阻む。
SNSは、この壁を破る格好の場である。
私はトランプ大統領やマクロン大統領、あるいは英国のアーティストや米国のコメンテーターなど、
興味のある英語・フランス語圏の発信者をTwitter(X)でフォローしている。
毎日、彼らの言葉を目にするだけでも、“違和感のない英語”が身体に馴染んでくる。
YouTubeも同様だ。
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド――どこの国の英語でも構わない。
興味のあるテーマを英語で聴き、聞き取れなければ巻き戻して何度でも聞く。
この繰り返しが、いわゆる「慣れ」をつくる。
第5章 公教育の誤りを脱する
英語を学び直す人がまずやるべきことは、
「学校で習った英語」をいったん忘れることだ。
昭和の英語教育は、英文法を厳格に守ることを目的としており、
「情報を伝える」という言語の本質から遠ざかっていた。
英語でもフランス語でも中国語でも、
最初の段階から文法の正確さを求める必要はない。
言葉とは、だいたい通じれば十分なのだ。
第6章 理屈コネ太郎式・実践ステップ
SNSで3人フォローする
興味のある分野の英語話者をフォローし、日常的に英語を目にする。YouTubeで毎日10分
英語字幕ON/OFFを切り替えながら視聴する。「あ、言えそう」と思った文をメモ
これが自分専用の“800文”の原石になる。コメントや短文投稿で使ってみる
間違いを恐れずアウトプットする。「完璧さ」ではなく「慣れの総量」を追う
量が質をつくる。気づけば理解が後から追いつく。
第7章 留学しなくても“異文化”はつかめる
外国語習得において、「留学」や「英語圏に住むこと」が必須というのは誤解だ。
SNSやYouTubeのように、世界中の人が母語で発信している時代、
英語を使う場は無限にある。
わざわざ国を出なくても、“情報の現場”にはいくらでもアクセスできる。
重要なのは、外国語を“勉強の対象”にしないこと。
「何か好きなことをもっと知りたいから仕方なく外国語を使う」
――その姿勢こそ、最も効率よく外国語を身につける方法である。
結論:理解よりも慣れ、完璧よりも継続
言葉は、頭で覚えるものではなく、身体で慣れるものだ。
新しい文法や単語にいちいち立ち止まらず、
「まあ、そんなもんか」と受け流すくらいでちょうどいい。
“慣れ”の総量が増えれば、
どんな言語もある日突然、自然に理解できる瞬間が訪れる。
そのとき、あなたの世界の地図は確実に広がっているはずだ。