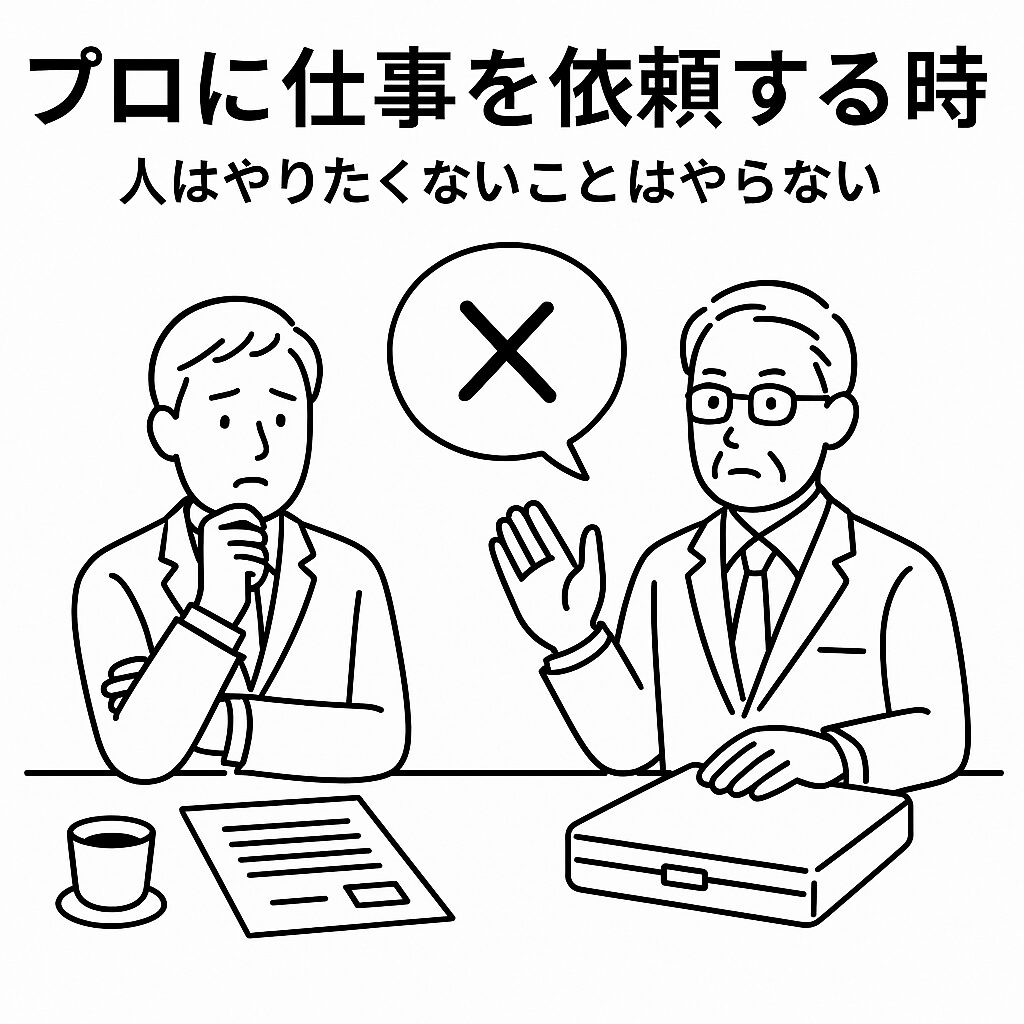Contents
1. 定型取引と非定型取引の違い
私たちは、ファーストフードの定型取引に慣れている。
メニューを選び、料金を支払えば、決められた商品やサービスが提供される。
そこには交渉も駆け引きもない。
この「お金を払えば確実に得られる」という仕組みは便利で、
現代人の多くはこの感覚を無意識に他の場面にも持ち込んでいる。
しかし、弁護士、税理士、公認会計士、医師、整備士などのプロフェッショナルの仕事は、
この定型取引とはまったく性質が異なる。
彼らが扱うのは、案件ごとに内容も手間もリスクも異なる非定型の業務だ。
したがって、依頼とは「定型サービスの購入」ではなく、
一人の人間に、その知識と時間と意欲を貸してもらう行為である。
同じ「お金を払う」でも、
マクドナルドでハンバーガーを買うのと、弁護士に助言を求めるのとでは構造が違う。
前者は「価格で成立する取引」、
後者は「関係性で成立する協働」だ。
ここを取り違えると、依頼の段階からすれ違いが始まる。人間は、やりたくないことは報酬を提示されてもやらない――この単純な事実を、まず理解してほしい
関連記事➡目上の人に相談するリスク【若いビジネスパーソン向け】
2. プロの仕事と「やりたくないこと」の現実
弁護士、税理士、公認会計士、医師――
こうした専門職には、職業倫理や法律によって「正当な理由なく依頼を断ってはならない」という原則がある。
表面上は、依頼があれば応じる義務があるように見える。
しかし、彼らも人間である。
法や規範がどう定めていようと、心の中では「やりたい仕事」あるいは「やってもよい仕事」と「やりたくない仕事」を区別している。
その判断は、単なる好みではなく、
報酬との釣り合い、手間やストレスの度合い、長期的なビジネス展開への影響、
あるいはこれまでの経験からくる直感的な予測――
そうした多層的で多元的な価値基準によって決まる。
プロフェッショナルが仕事を引き受けるのは、
その案件が「やりたい」あるいは「やってもよい」と判断された場合に限られる。
逆に「やりたくない」と判断された仕事は、
どんなに制度上は断れない立場であっても、実際には引き受けないか、
引き受けても熱意と質が下がる。
ここに、規範と人間性の乖離がある。
制度は「やれ」と言い、人間は「やりたくない」と思う。
その間で、プロは曖昧な表情と丁寧な言葉で均衡を取る。
そして依頼者は、その“やりたくなさ”を見抜けず、
報酬さえ払えば前に進めると誤解する。
3. プロは「やりたくない仕事」を言外に断る
プロは依頼を受ける前のヒアリングに熱心だ。
これは、依頼内容が自分の興味や専門性に合うかどうかを見極めるためである。
ところが、話を聞くうちに「これは面倒そうだ」「成果が見えにくい」「面倒くさそうな依頼人だ」と感じた瞬間、
態度が変わることがある。
表向きは「その件については後日連絡します」「方針が合わない」「時期が合わない」と言うが、
本音は「やりたくない」。
人間は本心を本心だからこそ口にしない。プロも例外ではない。
4. お金では動かないプロ
報酬を上げれば解決すると思うのは依頼者側の発想だ。
だが、プロはお金だけで動くわけではない。
興味のない仕事、ストレスの多い案件、リスクばかり高く成果が読めない仕事には、
いくら報酬を積まれても動かない。
それは、収益性よりも**自己効率と reputational risk(評判のリスク)**を重視する合理的判断だ。
一度“やりたくない仕事”を無理に引き受けて後悔した経験がある人ほど、
金では動かなくなる。
経験がプロを慎重にする。
5. お金に困っているプロにも注意
逆に、お金に困っているプロは「やりたくない仕事」あるいは「出来もしない仕事」でも受けてしまう。
このタイプは、最初こそ熱心に見えるが、途中で集中力が切れたり、成果の質が安定しないことが多い。
やりたくないのにやっているプロほど危うい。
依頼する側から見れば、安請け合いする人ほどリスクが高いことを理解しておく必要がある。
6. プロは「一件」ではなく「将来」で判断する
プロフェッショナルは、目の前の案件だけを見ているわけではない。
一見すると受けてもよさそうな依頼でも、その案件を引き受けることでその後のビジネス展開に支障が出ると判断すれば断る。
逆に、個別の案件としては割に合わなくても、
その依頼を通じて新しい分野への足がかりが得られると判断すれば引き受ける。
つまり、プロの「やりたい・やりたくない」は単発の感情だけでは決まらない。
長い経験のなかで磨かれた**独自の価値基準(物差し)**によって測られる。
その物差しで見たとき、仕事は「やりたい」「やってもよい」「やりたくない」と段階的に整理される。
判断は感情的ではなく、戦略的だ。
7. やりたいプロを探すほうが早い
プロは、なぜ仕事を引き受けるのか、あるいは断るのかを依頼者に正確に説明することはほとんどない。
動機が複雑で、説明が手間だからだ。
そのため依頼者は、プロが「やりたくない」と思っていることに気づかず、
なんとか説得すれば動いてくれると考えてしまう。
しかし、やりたくない人を説得して動かすより、最初からやりたい人を探す方が早い。
義務感で動く人と、自発的に動きたい人とでは、結果の質もスピードも違う。
依頼とは、相手を動かすことではなく、相手が自発的に動きたくなる条件を整えることなのだ。
8. 断られているのに、断られていると気づかない
依頼者は、プロがなぜ断るのかを理解できない。
さらに多いのは、断られていること自体に気づかないケースだ。
プロは露骨に「お断りします」とは言わない。
そのかわり、結論を先延ばしにしたり、論点をずらしたりして、
依頼者が自分から離れていくのを待つ。
「今は時期的に難しい」「少し検討させてください」といった言葉は、
実質的にはやんわりとした拒絶である。
依頼者はそれを真に受けて、「慎重な人だな」としか思わない。
本当はその時点で、プロは案件を受ける気がない。
プロの側も、断るのはストレスだ。
プロがはっきり断らないのは、単に気を遣っているからではない。
明確な拒絶は、依頼者との関係を損ねたり、「冷たい人」「不親切な人」と評判されるリスクがある。
つまり、プロの慎重な言葉づかいは、トラブルを避けるための防御反応でもある。
職業倫理や業界慣習上、無下に断ることが許されない。
評判を気にする立場であればなおさら、
はっきり断るよりも、依頼者を自然に諦めさせる方が安全だ。
こうして、両者は礼節を保ったまま、
それぞれ別のストレスを抱える。
依頼者は「進まないこと」に、プロは「断れないこと」に疲れていく。
9. まとめ
プロの世界では、制度上の義務と人間としての動機が常にせめぎ合っている。
やりたくない仕事は断りたい。
しかし、立場上それを明確には言えない。
だから、断られているのに断られていないように見える構造が生まれる。
依頼者がその構造を理解できれば、
無駄な説得や期待をせずに済む。
そして、本当に熱意を持って関わってくれるプロと出会える確率が上がる。
やりたくない人にやらせる努力より、やりたい人を探す努力をした方が合理的だ。
プロに仕事を依頼する際は、相手がその案件を「やりたい」あるいは「やってもよい」と考えているかを見極めよう。
ときには、「私の依頼内容は先生の見立てではスジが悪いですか?」と率直に尋ねてもいい。
その一言で、プロの防御姿勢が少し緩み、正直な見立てを聞けることがある。
もしその見立てが自分の考えとかけ離れているなら、礼を述べて退き、別のプロを探すほうがずっと合理的だ。
それが、現代の「プロとのつきあい方」の基本である。
人間は、やりたくない事は報酬を提示されてもやらない。プロでもそうなのだから、部下や後輩、子供や配偶者も同様だ。この事は人間の基本原理として理解して損はないと理屈コネ太郎は考える。
関連記事➡上手な質問の仕方|理解の準備があなたの評価を上げる