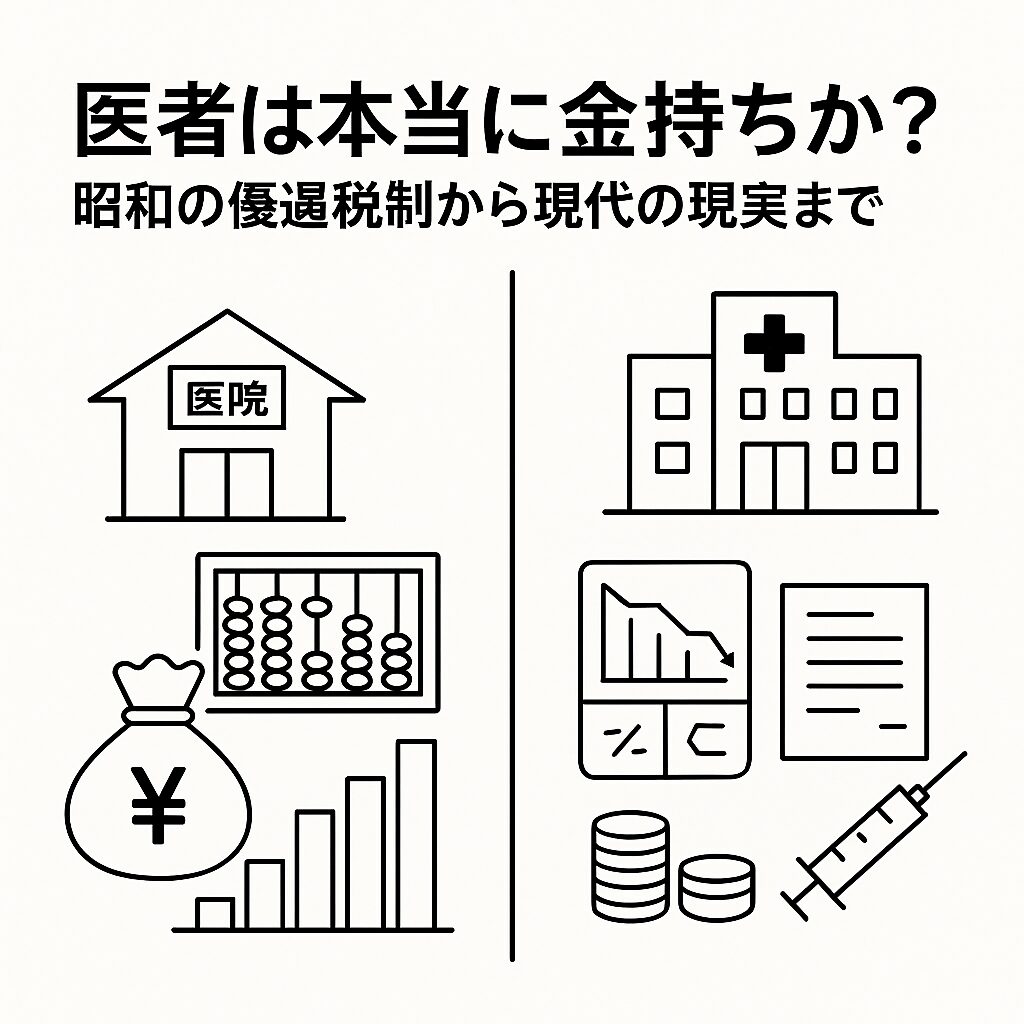結論から言えば、かつて医者が金持ちだった時代は確かにありました。しかし現代では、医師の多くは“中の上”程度の収入にとどまり、今後さらに先細りの傾向が強まるでしょう。以下に、勤務医と開業医両方の経験をもつ、理屈コネ太郎の管見内の私見を、やりがいなどの定性情報を一切含まずに、まとめます。
Contents
序章:医者=金持ちという神話
「医者は金持ち」。
この言葉は、長らく日本社会に根強く残ってきました。
しかし、現代の医師たちを見渡すと、必ずしもそうとは言い切れません。
この神話が生まれた背景には、昭和40~60年のころに医療機関が極めて高収益を上げ、実際に医師が裕福だった時代が存在したことがあります。本稿では、その時代の制度的な仕組みから現在の収益構造、そして「金持ち医師」と「そうでない医師」の実際の分布までを整理してみます。なお、本記事では便宜上、高収入=金持ちとして論を勧めます。
第1章:医者が本当に金持ちだった時代
昭和期の医療業界は、いくつかの制度的優遇措置に支えられ、極めて恵まれた構造を持っていました。その主な要因は次の3つです。
1. 医療機関優遇税制(租税特別措置法第7条ノ10)
昭和のある時期、医療機関には「保険診療による報酬の72%を自動的に経費として控除できる」という特例がありました。つまり、課税対象となるのは売上の28%だけ。
これにより、医療機関の実質的な利益率は極めて高く、医師が大きな財産を築くことができたのです。
2. 国民皆保険制度の導入(昭和36年)
1961年に整備された国民皆保険制度により、誰もが医療を受けられるようになりました。
潜在患者が一斉に受診者へと変わり、医療機関の収益は安定的に拡大。
しかもその収益は、前述の税制優遇により、ほとんど課税を受けない“準非課税収入”に近い状態だったのです。
3. 薬価差益という“もうひとつの収入源”
当時の医療機関は、薬を安く仕入れて、国が定めた薬価で患者に提供する仕組みでした。
薬価と仕入れ値の差が医療機関の利益となる――これが「薬価差益」です。
薬価は一律で決まっていたため、ほとんどの医療機関で確実な利益が発生していました。
こうした制度的な追い風のもと、医療機関の経営は黄金期を迎え、医師=富裕層というイメージが社会に定着したのです。
第2章:優遇の終焉と現代の収益構造
しかし、これらの恩恵はすでに過去のものとなりました。
優遇税制の廃止と限定化
かつての「医療機関優遇税制」はほぼ廃止され、現在は租税特別措置法第26条に限定的な形で残るのみです。
対象は過疎地の診療所や新設の小規模クリニックなどに限られ、大規模医療法人にはほとんど適用されません。
薬価差益の縮小
厚生労働省が定期的に全国調査を行い、薬価を現実の卸価格に近づけて調整するようになったため、かつてのような差益はほぼ消滅しました。
現代の開業医の経済状況
医療機関の経営は低調で、特に都市部の開業医では人件費や設備投資がかさみ、収支はギリギリというケースも珍しくありません。さらに、診療報酬の抑制政策により売上の伸びも限られるため、結果として開業医の可処分所得は高くありません。
現代の勤務医の経済状況
在籍する医療機関の経営が低調なので、給与は高くなりようがないのが現実です。キーエンスや三菱商事の平均給与が2千万円を超える現代では、勤務医の給与は低いとは言えないだけで、高いとも言えないのが現状でしょう。
第3章:それでも一部は金持ち ― 医師格差の実態
「医者は金持ちではない」という言説は、半分だけ正しいのです。
なぜなら、今もなお“金持ち医師”は確かに存在するからです。
その差を生み出すのは、次の3つの要素です。
親に資産があるか(=スタート地点の差)
親が医師で、昭和期の資産を受け継いでいるケースでは、土地・建物・法人などの資産から安定した副収入があります。学費負担・返済義務の有無
医学部の学費は高額で、私立では6年間で3000万円を超えることもあります。親が学費負担をしても、医師になった後に返済している医師も多くいます。
親が援助できない場合、奨学金や教育ローンで学費を賄い、卒後に返済を背負う医師も少なくありません。本人の所得(診療科・勤務形態・自由診療)
美容医療や自由診療分野では、保険診療に比べて高収益を得る医師もいます。
一方で、勤務医として保険診療を続ける限り、年収2000万円を超えるケースはまれです。
第4章:確率で見る「金持ち医師」
ここで、少し理屈っぽく考えてみましょう。
「金持ち」を仮に「平均所得+1σ(上位16%)」と定義すると――
医師のうち約半数がこの上位16%に入る。
残り半数は平均より上だが、「金持ち」とは言えない。
つまり、「医者=金持ち」は半分だけ本当なのです。
この分布を決めるのは、先述した「資産」「負債」「所得」の三要素の組み合わせ。
特に「親が金持ちで、学費返済がなく、本人も高収益分野で働く医師」は、**所得分布の上位18%**に入る確率が高い一方、
そうでない医師は「中の上」止まりというのが現実です。
第5章:医師という職業の“安定”という価値
それでもなお、医師という職業には確かな安定があります。
なぜなら、国の制度設計そのものが――
医療機関を“裕福にも貧困にもさせない”ように作られている
からです。
医師が国民皆保険制度の枠内で保険診療を行う限り、極端な困窮に陥ることはありません。
反面、過度な利益を得ることもできない。
つまり、国は医療の公共性を守るために、医師を“安定的な中流上位層”に位置づけていると見ることができます。
結論:医者=金持ちは半分だけ本当
昭和のような優遇税制も薬価差益も、いまや過去の話。
現代の医師は、もはや“特権階級”ではありません。
しかし、健康保険制度がこのまま継続すれば安定した職業であることは間違いなく、確率的に見れば「金持ちに入る可能性が高い職業」と言えます。
つまり――
「医者は金持ち」は、半分だけ本当。
そして、「半分だけでそれなりに幸せな職業」でもあるのです。
医者を目指す人も、医療を支える立場の人も、「制度が作る安定」と「努力が生む差」の両方を理解しておくことが、これからの時代に不可欠です。