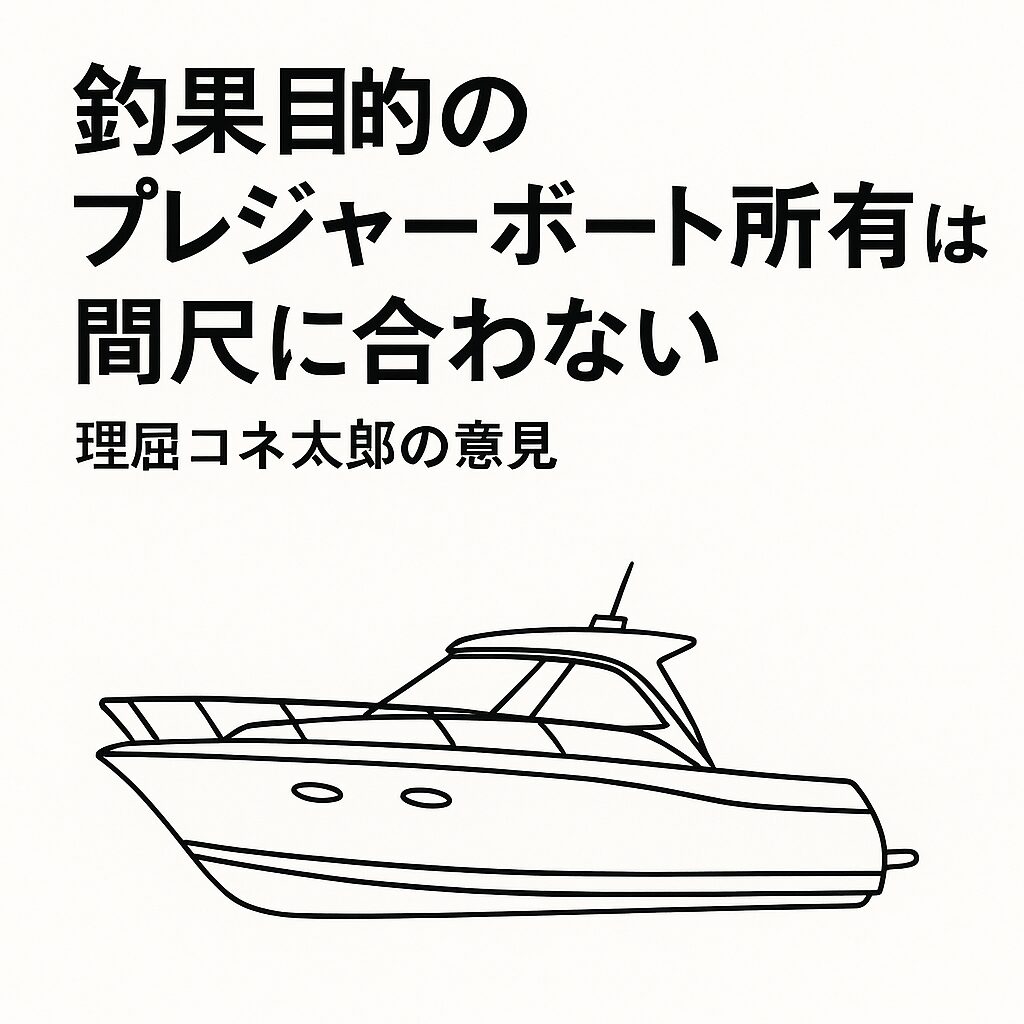Contents
第一章 はじめに:海に惹かれる心と現実の狭間で
釣り人なら、船で沖に出て好きなだけ釣りを楽しみたい。そう思うのは自然なことである。
狙ったポイントへ自らの意志で舵を取り、思うままに竿を出す――その夢を抱いてプレジャーボートの購入を検討する人は少なくない。
しかし、夢と現実のあいだには、しばしば深い隔たりがある。
とくに「釣果を上げるためにボートを持つ」という発想は、心情的には理解できるが、実際には経済的合理性と心理的満足に欠ける選択なのかも知れない。
さらに、その延長として「維持費の足しにするため、こじんまりと遊漁船でもやってみよう」と考えることは、プレジャーボート購入を検討する釣り人なら当然の帰結だが、
実際にはそれもまた、次の段階の誤算である。
本稿では、釣果目的のボート所有と、副業的な遊漁船経営という二つの錯覚について、静かに整理してみたい。
第二章 釣果目的のボート所有が成立しにくい理由
プレジャーボートは、所有した瞬間から維持が始まる。
燃料費、マリーナ保管料、保険、定期整備――これらの支出は決して少なくない。
仮に年に二十回ほど出航したとしても、年間の経費を出航回数で割ると、一回あたりの実質コストは十万円を超えることも珍しくない。
それに対し、遊漁船で同程度の釣りを楽しむ場合、費用は一回一万円前後で済む。
しかも、準備も後片づけも不要で、安全管理も船長任せである。
この差は、数字の上でも心理の上でも大きい。
さらに、プレジャーボートでは海況や機器トラブルなどにより出航できない日が必ず生じる。
一年を通して安定して航行できる機会は思いのほか少なく、加えて修理や改修に時間を取られることもしばしばである。
つまり、実際の「釣りに使える日数」は想定の半分以下になることもある。
そして何より、船の所有が「釣りの効率」を上げるわけでもなく、「釣る楽しみ」を増加させるわけではない。
釣果を目的にボートを買うのは、結果として“もっとも高価な釣り具”の購入なのかもしれない。
第三章 副業としての小規模遊漁船という発想について
釣り人がプレジャーボート所有を検討するとき、しばしば次のような考えが抱く。
「ときどき友人や知人を乗せ、それなりの謝礼を得られれば維持費の助けになるのではないか」と。
その思いは理解できる。船の維持には相応の費用がかかり、海に出る機会を有効に活かしたくなるのは自然な心情である。
しかしながら、実際にはこの小規模な遊漁船という形態は非常に成立しにくい。
小型艇での少人数運航では、受け取る金額が燃料費や保管料にほぼ吸収され、収益が残らないのが普通である。
しかも、たとえ相手が友人であっても、金銭を受け取った瞬間に関係は趣味の延長から「営業」へと転じる。
そのとき船長が負う責任は重く、事故や怪我が生じた場合のために保険加入が必須だが、保険料も小さくない。
多くのプレジャーボートのオーナー達が遊漁船を営まないのは、コスト的に全く見合わないからなのだ。もしかしたら、保険会社に高リスクとみなされて加入を拒まれることもあり得る。
さらに、考えてみたいのは顧客の側の視点である。
果たして、わざわざ料金を払ってまで、知人の小さなプレジャーボートに乗りたいと思う釣り客がどれほどいるだろうか。確実に釣らせてくれるか、安全対策は万全なのか…。
狭いデッキ、簡素な装備、揺れの大きい船体――その環境で一日を過ごすことを好む顧客のボリュームは小さいだろう。
釣り客は一般に「釣果」と「快適さ」を求める。
そのいずれの点でも、小規模艇は本格的な遊漁船に及ばない。
つまり、小さな船で小さな料金を受け取り、わずかな人数を相手にするという構想は、
提供者側だけでなく、利用者側にも強い動機を生みにくいのである。
経済の両面が細く、安定しない――それが小規模遊漁船という構想の宿命である。
第四章 数字が示す経済構造の現実
具体的に計算してみよう。
仮に24フィート級の船に三名を乗せ、一人あたり一万円を受け取るとする。
年に三十回出航しても、年間の総収入は九十万円にとどまる。
一方で、燃料費・オイル・係留費・保険・整備費などの必要経費は、
控えめに見積もっても年間百五十万から二百万円。
この時点で、明確な赤字が生じる。
だから、削減できる固定費である係留費や保険料などを削減すべく、出来るだけ廉価な場所や保険を探す事になるのだが、
おそらく条件にあう係留場所や保険を見つけるのは、不可能とは言わないがかなり困難だろう。
非公式な運営であっても、この構造は変わらない。
むしろ法的整備を怠ることで、事故時の補償責任を全て個人が負うことになり、
「儲からない上に、危険だけが残る」状態となる。
経済合理性の観点から見れば、
小規模遊漁船は副業ではなく、採算の取れない労働である。
その構造を理解してなお挑むのであれば、それはもはや事業というより信念の領域に属するだろう。
第五章 釣りを楽しむ船と、人を乗せる船との違い
自分の釣りを楽しむための自分の船と、釣り客を乗せるための自分の船は、目的も背負う責任も大きく異なる。
責任を引き受ける対価も、釣り人の支払う料金に含まれていると考えるのが普通だ。
小型艇の船長にとって、航行の安全、潮流の判断、船位の維持は片時も気を抜けない作業であり、
自ら釣りを楽しむ余裕はほとんどない。
釣果を上げるよりも、事故を起こさず帰港することが最優先となる。
その現実を踏まえれば、「自分も釣りながら客も案内する」という発想は、
経験豊富な船長であっても容易ではないことが理解できるだろう。
第六章 結論:釣り目的で船を買うと超高額釣り具になってしまう
釣り人がボート購入を検討すること自体は、極めて自然だと理屈コネ太郎は思う。
それは海との関係を深め、自然と向き合うための貴重な体験でもある。
しかし、そこに「釣果」や「収益回収」といった打算を持ち込むと、
次第に海が数字に見え、楽しさが義務に変わってゆく。釣りをボートの入り口と考えると、色々と間尺に合わない事が多いのだ。
釣りが本来持つ愉しみや自由さが、プレジャーボートにまつわる様々な費用やルールに棄損されるからだと理屈コネ太郎は考えている。
釣りを基点にボートを検討するのなら、カヤックかジェットスキーが釣具として最大許容範囲かも知れない。これらなら、家のガレージに置けるし、保管施設も船よりは全然リーズナブルだ。
釣りを出発点として考えると、プレジャーボートは釣りを楽しくするが、費用を負担する苦しみがその愉しみを遥かに超えてしまう事が多い。
そして、この間尺の合わなさすらも愉しめる人は、あるいは自分だったら絶対にうまく経営してみせると自身のある人は、ぜひ挑戦を続けてほしい。間尺に合わない遊びを楽しめる人には、困難にチャレンジする人は、間尺にあった行動しかしない人には垣間見れない世界に立つチャンスがあるはずだから。
そこには、合理を超えた喜びがあり、海と人との新しい関係が待っている。