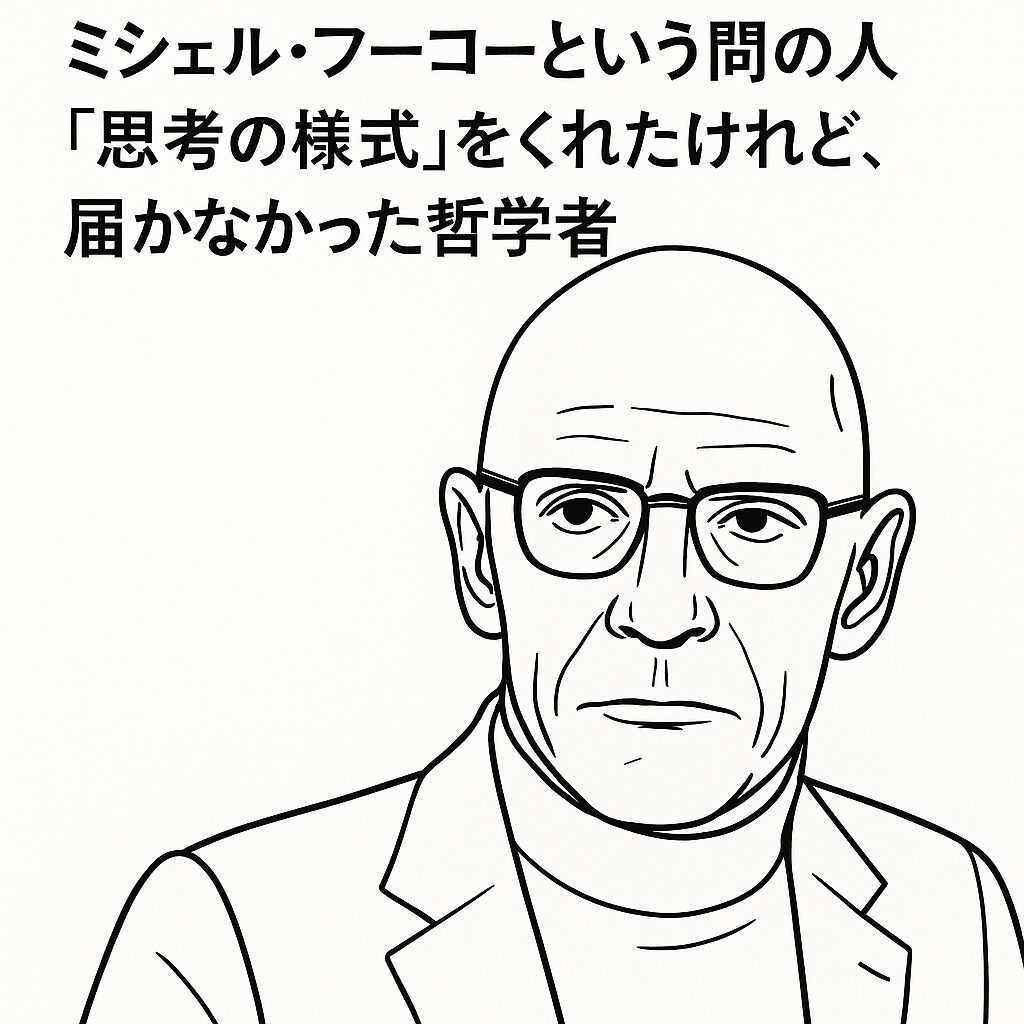Contents
はじめに|彼の言葉は難しい。でも、それだけで切り捨てていいのか?
ミシェル・フーコーというフランスの思想家がいます。
一般にはあまり知られていないかもしれません。彼の書いた本は非常に難解で、読もうとするとたいていの人が挫折します。
それでも私は、彼が私たちに「ひとつの思考の様式」を残してくれたことには、大きな意味があると思っています。
それは、何を信じるべきか、どう生きるべきかといった「答え」ではありません。
むしろ、世の中の「当たり前」や「常識」がどのように形づくられてきたのかを疑い直す、“問い方”のスタイルです。
フーコーが私たちに残したもの:それは「問い」の姿勢だった
彼の思索が扱ったテーマは非常に多岐にわたりますが、その根底には一貫してある“問いの形”がありました。
フーコーは、「狂気とは何か」「犯罪とは何か」「性とは何か」といったテーマを扱いました。
けれど彼が本当に問いたかったのは、その言葉の中身ではなく、**その言葉が“どうやって社会の中で形作られてきたのか”**ということです。
たとえば、「精神病」という言葉。
今では医療用語として定着していますが、フーコーはそこに立ち止まりました。
そもそも、誰が「狂っている」と決めるのか?
なぜそれを病と名づけ、施設に隔離するようになったのか?
彼はこのように、「誰が語るか」「どこから語るか」「何が語られないのか」という視点で社会を読み解こうとしました。
これが、彼の残した思考の様式です。
目の前にある制度や言葉の背景にある構造を、静かに問い直すスタイルです。
でも、どうしてこの思考は私たちに届かないのか?
問題はここからです。
このフーコー的な思考スタイルは、私たちの社会にはほとんど届いていません。
届かない理由は、いくつかあります。
彼の書いた文章がとにかく難しく、抽象的で、わかりづらい。
即効性のある知識を求める現代人にとって、彼の著述は極めて難解で時間がかかる。
教育・医療・行政などの現場でも、フーコー的視点は理解しにくく、使いにくい。
要するに、彼の思考は人々に届くにはとにかく難解だったのです。
「思考」が届かないということの意味
けれど私は、それでも彼のような思想家が存在したことには意味があると思います。
なぜなら、私たちはふだん、「社会とはなんとなくこういうもの」「人間とはなんとなくこうあるべき」といった形で、言葉にされないルールに従って生きています。
そのルールがいつ、誰によって、何のためにできたのかを問わぬままに。
フーコーの仕事は、そうした沈黙の構造(言葉にされないルール)に、静かに光を当てるものでした。
誰かが気づき、誰かが問う。それだけで十分かもしれない
フーコーの考え方は、宗教のように「救われたい人」に明確な答えを与えてはくれません。
彼はむしろ、「答えがあまりにも簡単に用意されすぎていること」を疑う哲学者でした。
彼の言葉は難しく、近寄りがたいものです。
でもその奥にある「問いの姿勢」だけは、誰にとっても静かに触れる価値があるのではないでしょうか。
目の前にある当たり前を、ほんの一歩引いて見つめる。
自分の「常識」が、もしかしたら誰かを苦しめているかもしれないと想像する。
ほんの一歩引いて見つめる事は、彼の時代にはまだあまり知られていなかったメタ認知なのかも知れません。メタ認知については『「認知の歪み」は人間理解のカギ|人との付き合い方が変わる心理学的視点』を参照してください。
こうした問いの姿勢は、社会を一気に変えることはなくても、「変えることができるかもしれない」と思うための小さな地図にはなるはずです。
人物としてのミシェル・フーコー──社会の外縁を生きた知性
輪郭を持った異端者として
フーコーは1926年、フランス西部の医師の家に生まれました。
幼少期から抜きん出た知性を示しつつも、深い孤独を抱えていた人物です。
自らの性的指向(同性愛)と精神の脆さ、社会との距離感。
フーコーは「社会に適応しない者」としての自己像を内に持ちつつ、それを叫ぶのではなく、静かに、しかし根深く問い続ける形で思想へと変換していきました。
エリートでありながら、どこにも属さなかった
彼はパリの名門エコール・ノルマル・シュペリウールで哲学と心理学を学び、
その後はスウェーデン、ポーランド、チュニジアなどを転々とした後、パリ第8大学で教鞭をとり、最終的にはフランス最高峰の知的機関、コレージュ・ド・フランス「思想史」講座の教授に就任します。
しかし彼は、伝統的な学派にも政治グループにも帰属せず、つねに制度の“脇”を歩く知性でした。
欧州文化とフーコー──内部から解体する知のかたち
彼が解体しようとしたのは、他でもない西洋の理性主義、ヒューマニズム、キリスト教的主体性でした。
「狂気とは理性によって排除されたもうひとつの声である」
「自由は、語らせ、記録し、監視する構造の中に生まれる幻想である」
「“人間”という概念は、近代が発明した最近の発明品にすぎない」
彼は欧州の知の伝統を憎んだのではなく、その限界を最も深く知る者として内部から照射し続けたのです。
アメリカで見つけた「身体と思索の自由」
1970年代末、フーコーはカリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとるなど、アメリカに頻繁に滞在するようになります。
彼は当時のサンフランシスコのゲイ・カルチャー、レザー・コミュニティ、都市のサブカルチャーに衝撃を受け、そこに新しい「生の技法」の可能性を見出します。
晩年の彼の思索──「性の歴史」や「自己への配慮」「主体の形成」などは、この経験と密接につながっています。
彼は自由を求めたのではなく、自分で自分を形づくる実験の場として、性愛や身体性を哲学に接続しようとしていたのです。
沈黙の死──語られざるものを追った者の終焉
1984年、HIV感染によりパリで死去。
当時はまだ「エイズ」という病が正式に語られることすら差別や恐怖を招く時代でした。
公的には「神経障害」とだけ発表された彼の死は、まさに彼が生涯追ってきたテーマ、すなわち「語ることと語られないこと」「制度と身体」「告白と沈黙」が交錯する場所だったと言えます。
彼は死に際しても、何も語らなかった。
沈黙を強いられたのではなく、沈黙を選んだのかもしれません。
おわりに|届かないものの意味を、いま一度考えてみる
フーコーの思考は、私達が生きているこの社会に「実装」されたとは言えません。それは、たしかに届きませんでした。
でも、こうして誰かが彼のことを語り、読もうとし、
「それでも意味があるのではないか」と問うだけでも、
その思想は、小さなかたちで生き続けているのだと思います。
届かなかったことそのものが、私たちに考える余地を残している。
フーコーという哲学者は、そんな余白を残した「問いの人」だったのです。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ
▶筆者紹介は『理屈コネ太郎の知ったか自慢|35歳で医師となり定年後は趣味と学びに邁進』からどうぞ。