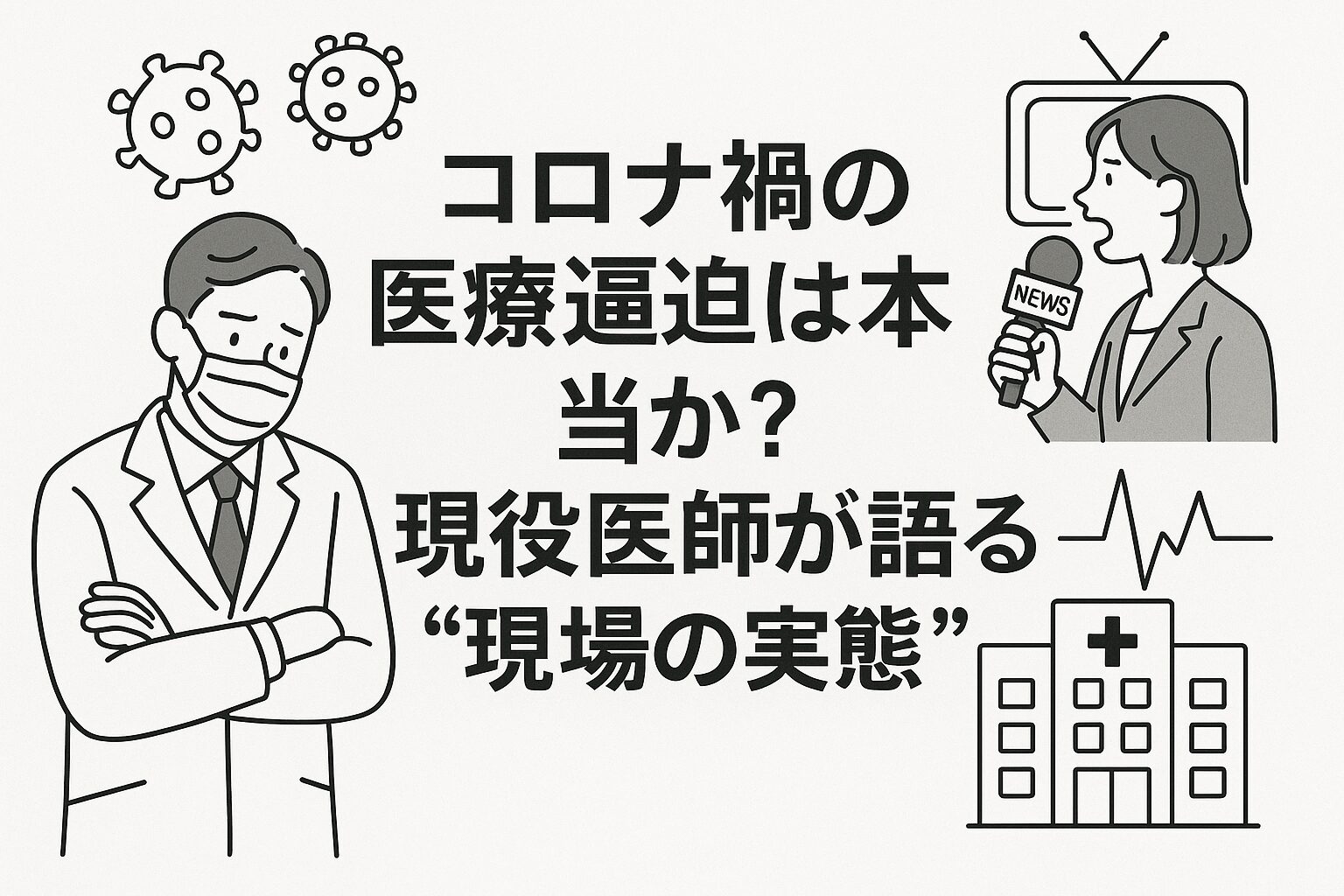Contents
はじめに:医療逼迫と不安を煽る報道への違和感
※本記事は2021年1月30日に執筆されました。
「医療が逼迫している」との報道が2020年末から2021年初頭にかけて多く流れ、人々の不安を一層高めました。しかし、現場に立つ医師としての『理屈コネ太郎』の肌感覚では、医療“全体”が逼迫しているとは到底思えません。
今回は、現役医師としての実感と観察をもとに、「逼迫」と言われる状況の内訳と、その本質に迫ります。
医療逼迫の“構造”とは何か?
「医療全体」ではなく「一部のコロナ診療部署」が逼迫している
筆者は急性期病院で消化器を担当していますが、日々の診療(胃がん、大腸がん、胃潰瘍、虫垂炎、胆嚢炎など)はコロナ以前と変わらず粛々と行われています。
逼迫しているのは、医療全体のうちごく一部——コロナ診療に直接関与している部署だけなのです。
通常医療の現場は“プロフェッショナルに通常運転”
面会制限や消毒作業といった業務上の変化はあっても、医療の基盤部分は崩れていません。日本の医療者は各自の持ち場を守り、普段通りの診療を続けています。
バイデン大統領の演説が与えた衝撃と違和感
アメリカと日本ではコロナの“悪性度”が違う?
バイデン大統領の就任演説で「第二次世界大戦で亡くなったアメリカ人より多くの命がコロナで失われた」と語られたことに、筆者は強い衝撃を受けました。
確かに米国では50万人近い死者が出ていますが、日本における感染状況や重症化率、死者数とは明らかに様相が異なります。
違いの原因はどこに?
この差の要因は不明ですが、以下のような仮説が考えられます:
- 医療体制や国民皆保険制度の有無
- 生活習慣や食文化
- 遺伝的な背景
つまり、日本でも今後「本当に悪性度の高い感染症」が流行する可能性は排除できないということです。そのリスクには、常に備える必要があります。
なぜ「医療崩壊」と叫ばれるのか?
報道の“視野”と“編集”の問題
メディアが伝える「逼迫」は、コロナ対応部署の現場感が日本の“医療全体”の状態であるかのように編集されて報道される傾向があります。
しかし実態は、全医療リソースの中でごく一部。胃潰瘍も急性膵炎も、胆嚢炎も、専門家がきちんと対応しています。読者は、こうした冷静な視野も持っておくべきです。
「困っている」と声を上げる人の構造的背景
ここで一歩立ち止まって考えてみてほしいのです。
「大変です!」「困っています!」と声高に発信している人たちは、本当に全員が困っているのでしょうか?
社会科学的に見た「助けを求める動機」
本当に困っている人も、そうでない人も混在する
無論、切実に困っている人はいます。医療従事者でも、患者数が急増すれば過重労働や精神的疲弊に直面します。
しかし社会科学の視点では、「あまり困っていないが“助けを得るために”困っているふりをする」という行動も珍しくありません。
情報発信の“動機”を見抜く力が必要
社会においては、「不安を煽る情報」や「過剰に大変さを訴える発信」が支援獲得や影響力維持の手段として用いられる場合があります。
この構造を正確に理解することが、情報に振り回されずに行動するために不可欠です。
(※この領域の議論は複雑なため、本記事では概要にとどめ、別記事で詳しく取り上げます)
まとめ:逼迫は“部分的現実”であり、“全体像”ではない
日本の医療現場は、全体としては崩れていません。コロナ対応部署の過密さが報じられる一方で、それ以外の領域では日々の診療が粛々と続いています。
報道のすべてが誤っているとは言いませんが、受け手が「情報の構造」を理解し、自らバランスを取る視点を持つことが重要です。
関連記事(“ココ”をクリック)
- 忙しい病院の上手な受診方法については → “ココ”
- 医療者に期待しすぎないためには → “ココ”
- 医者がせっかちな理由は? → “ココ”
- 看護師に嫌われるとどうなる? → “ココ”
- 高齢者の受診に付き添うときの注意点 → “ココ”