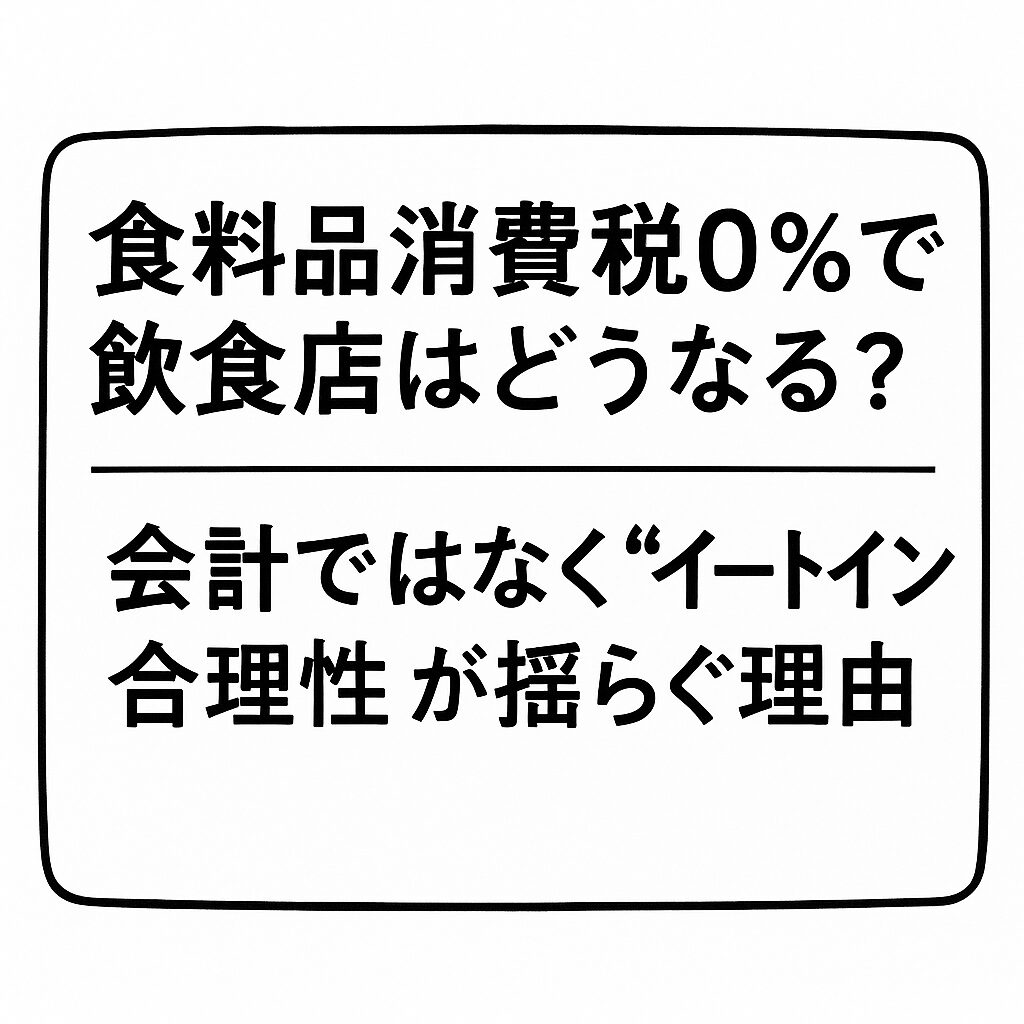食料品の消費税が0%になっても、イートイン飲食店の増税には繋がらない。ただし、消費税0%となると自炊やテイクアウトの方が割安と考える人が増えて、その結果、外食需要が減少する可能性はある。本記事では、その理由を市場心理と相対価格の構造からわかりやすく解説する。
Contents
はじめに:食料品0%は飲食店にとって増税にならないし利益も変わらない。
「食料品の消費税を0%にすると、飲食店にとって増税となり倒産が増える」といった主張を目にすることがある。この話は本当なのだろうか。
ネット記事の中には、次のように説明するものがある。
食材が非課税になることで、仕入れ時に払った消費税が控除できなくなり、飲食店の負担が増える。
しかしこれは誤解である。食料品が非課税または0%なら、飲食店はそもそも仕入れ時に消費税を払っていない。払っていない税金を控除できなくても、負担は増えない。詳細は 食料品消費税0%でも飲食店の税負担は変化なし|簿記・会計・税制から説明を参照。
■ 結論(先に明確に)
「飲食店にとって増税になる」──完全に誤解。
「飲食店がバタバタ倒産する」──これも会計的には誤解。
ただし、外食と自炊・テイクアウトの相対価格が変わるため、イートイン前提の店舗モデルの合理性が低下する可能性はある。
つまり 「会計的には影響ゼロ」「市場の変化には影響あり得る」 という構図である。
本記事では、ファイナンス修士でもある私・理屈コネ太郎が、
簿記・会計・市場行動の3点 から、この構造変化を“シンプルに”解説する。
(もちろん、あくまで私の管見内の私見にすぎないこともご理解ください。)
それでも外食が“割高”に感じられかねない理由
消費税0%で変わるのは 会計ではなく相対価格 である。客の心理というか受け止めかただ。
自炊のコストが下がる
テイクアウト食品部分の価格も下がる
イートインは変わらない
この結果、
「外食って高いよな」
「テイクアウトの方が賢いよね」
という心理が強まり、外食需要が揺らぐ可能性がある。
自炊・テイクアウトが相対的に優位になる構造
食料品が0%になることで、自炊とテイクアウト(食品部分)の価格が相対的に低下する。
一方、イートイン提供には
席
空間
手間
サービス
が伴うため、価格はそのまま。
“差” が生じることで、心理的な割高感が発生する。
イートイン前提の店舗モデルが最も影響を受ける
イートインにはテイクアウトにない 固定費 が存在する。
広い客席
家賃
ホール人件費
光熱費
席の回転率の制約
テイクアウトが増えると、これら固定費の回収が難しくなる。
稼働率が落ち、席数が過大投資へと転じる。
つまり起きているのは 「採算悪化」ではなく「イートイン前提モデルの合理性低下」 である。
席料やチャージが再評価される未来
イートインの「席」は本来コストを伴う資源である。
そのため、席料・チャージなどは固定費回収や稼働率リスクを緩和する合理的仕組みであり、
食料品0%の世界では、むしろその必要性がより明確になる可能性がある。
起こり得る変化:縮小・転換・ゴーストキッチン化
食料品0%が実施されれば、飲食店には以下の変化が起こり得る。
イートイン面積の縮小
イートイン営業の廃止
テイクアウト特化型への移行
ゴーストキッチン化
店舗移転
席料・チャージの再導入
セルフサービス化による効率化
これは「倒産の連鎖」ではなく、店舗モデルの最適化・構造転換 と捉えるべきである。
結論:動くのは会計ではなく“市場の心理と合理性”
会計上は何も変わらない
消費税負担も利益も変わらない
しかし相対価格の変化で外食が割高に見える
消費者行動が変化し、イートインの稼働率が下がる
結果として、イートイン前提の店舗モデルの合理性が低下する
食料品消費税0%が飲食店にもたらすのは、
会計負担の増加ではなく、どの店舗モデルが生き残るかという選別の開始である。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ