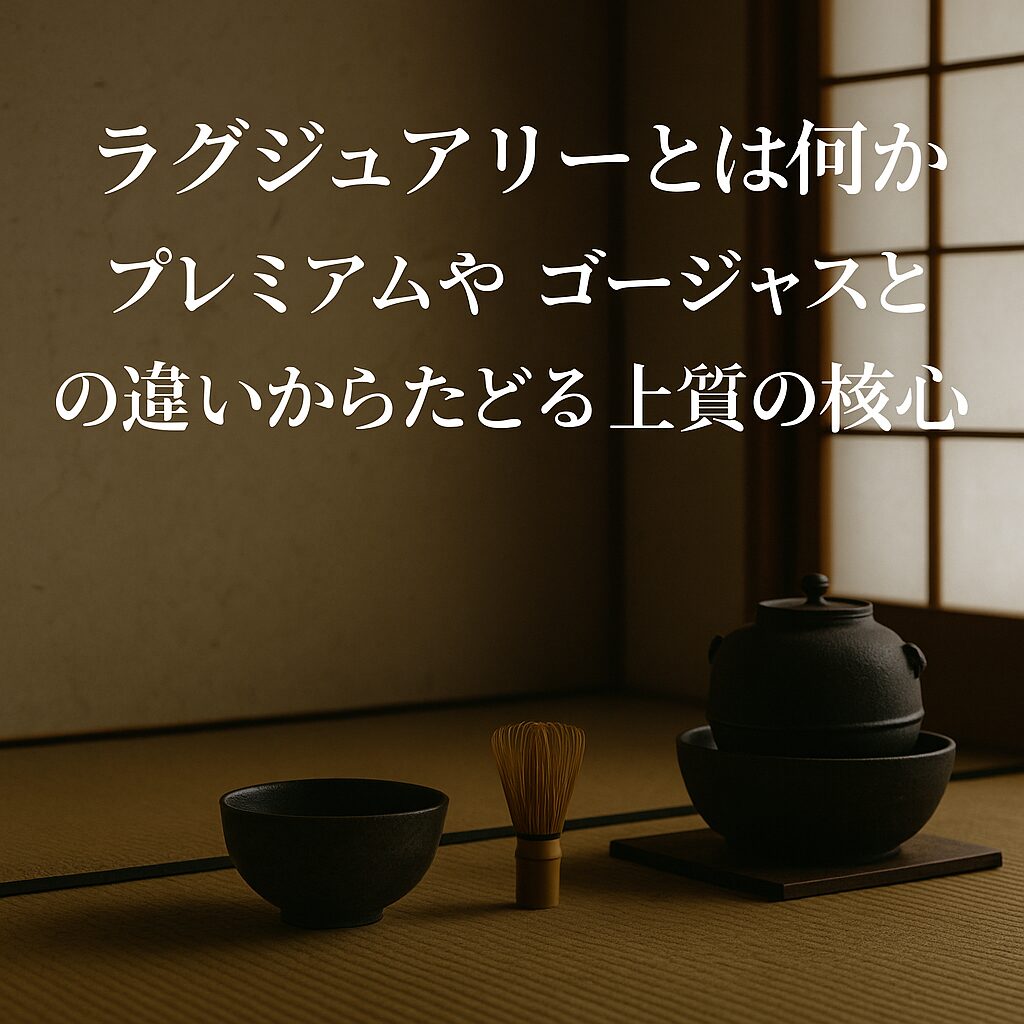本記事を読むと、ラグジュアリー体験の本質に近づける。プレミアムやゴージャスとラグジュアリーがどう違うかを明確にしたうえで、作品を通して作者の精神に感応する鑑賞者の心の在りようから、ラグジュアリーの本質を描出する。
Contents
■ 序章:まず「3者の違い」から整理する
「ラグジュアリー」「プレミアム」「ゴージャス」。
どれも“良いもの”を指すように聞こえるが、実はまったく違う概念である。
この3つを曖昧なままにしておくと、「ラグジュアリーとは何か?」という問いに到達できない。
そこで本記事では、まずこの3つの違いを整理するところから始めたい。
なぜなら、3つの違いを明確にすることが、
“上質とは何か” の本質へ近づくためのもっとも自然な入り口
になるからである。
以下、理屈コネ太郎の管見内の私見であるとご銘記のうえ読み進めて頂ければ幸いである。
【第1章】プレミアムとは──“等級”の話である
最初に言えば、
プレミアムとは「等級・グレード」を示す言葉である。
プレミアム席、プレミアムプラン、プレミアムビール……。
いずれも同一ラインナップの中で “上” に位置づけられたものという意味で使われる。
ここで大切なのは、必ずしも
プレミアム = 上質 ではない
という点だ。
プレミアムは単なる差別化のラベルであり、
体験の質を保証する言葉ではない。
したがって、ラグジュアリーとは別の次元の概念である。
【第2章】ゴージャスとは──“派手さ”の話である
ゴージャスは、
派手さや華やかさ を表す概念である。
キラキラした装飾
金色の質感
スパンコール
強い光沢や色彩
こうした“視覚刺激の強さ”が中心であり、
それが上質かどうかとは関係がない。
つまり、
派手なら下品でもゴージャス。
派手なら上品でもゴージャス。
というように、
ゴージャス=見た目の強さ でしかなく、
体験の上質さには関わらない。
【第3章】では、ラグジュアリーとは何か
プレミアムが“等級”、
ゴージャスが“派手さ”だとすれば、
ラグジュアリーはまったく違う性質を持つ。
ラグジュアリーとは端的に言えば、
“上質な感覚体験(quality of sensory experience)”のことである。
静けさ
整頓
清潔
光と影の深さ
温度の変化
手触りの密度
音の澄み方
時間の濃さ
こうした感覚要素が重なり、
体験者の内側で立ち上がる上質さ こそがラグジュアリーである。
ここで忘れてはならないのは、
ラグジュアリーが成立するには、体験者側にも条件があることだ。
ラグジュアリーが人の中で立ち上がるためには、
その体験を受け止めるための“小さなゆとり”を人は持たねばならない。
ここでいう“ゆとり”とは、
物理的な空間の空きではない。
静けさや光や手触りをきちんと受け取るための、
感覚が働きやすい“心の状態” のことである。
この「ゆとり」は、後に登場する茶室の理解にとって不可欠となる。
【第4章】ラグジュアリーは“受け手の素地”で変化する
ラグジュアリーが体験者の中に立ち上がる感覚である以上、
同じ経験でも、体験される感覚は十人十色だろう。
たとえばロレックスの重さや音の心地よさ、温度の変化を
“上質だ”と受け取る人もいれば、
“ただの金属の塊”としか感じない人もいる。
一方、パテックフィリップは、
歴史や文脈、仕上げの意味といった“文化的素地”がなければ、
価値が立ち上がってこない。
ロレックスは“感覚でわかるラグジュアリー”。
パテックは“素地が必要なラグジュアリー”。
この違いを通じて、
ラグジュアリーは、素地と選好によって解像度が変わる体験である。
という重要な視点が浮かび上がる。
ラグジュアリー体験は、芸術鑑賞とよく似ている。
観たり聴いたりする知覚上の愉悦だけでなく、
作品に宿る新しい技法や発想、
そしてその創造過程で作者が味わった葛藤へ想いを向ける姿勢が求められる。
ラグジュアリーもまた、
名の知られぬ設計者の美学が仕組みの中に潜み、
それに感応するための“素地”を受け手に要求する。
この“素地に応じて深さが変わる構造”が、
芸術鑑賞とラグジュアリー体験を貫く構造だ。
【第5章】侘び寂び──上質な感覚体験 × ゆとり × 救済
侘び寂びの茶室は、一見すると“質素”に見えるかもしれない。
しかし実際には、
清潔
整頓
光の扱い
影の深さ
静寂の保ち方
といった感覚要素を精密に整えた、
高コストの簡素 であり、
そこには“上質な感覚体験”が凝縮された
ラグジュアリー性を備えた空間 がある。
しかし、茶室のラグジュアリー性を理解するには、
戦国時代という歴史的文脈が欠かせない。
戦国の乱世は、常に緊張が絶えず、
“心のゆとり”がほとんど存在しない世界だった。
だからこそ、茶室の静逸は極めて希少だった。
そのような状況で、茶室に入る戦闘者は、
無意識のうちに“静逸への希求”を抱えていたはずである。
その希求に触れたとき──
茶室に備わった上質な感覚体験の仕組み──いわばそのラグジュアリー性は、
戦闘者たちが無意識に抱えていた“静逸への希求”に触れ、
その内側に小さなゆとりを開花させた。そのゆとりは、戦の緊張に凝り固まった心を一瞬だけほどき、
彼らにとって確かな救済として働いたのだと思う。
ここに、
上質な感覚体験(ラグジュアリー性)
ゆとりの開花
救済として働く
という 三段階の構造 がはっきりと現れる。
茶室は、乱世において
ラグジュアリーと救済が同時に顔を出す、きわめて稀な空間 だったのである。
茶室に“リラックス”はない。
そこにあるのは、戦国武将の心を支えた研ぎ澄まされたラグジュアリーである。
【第6章】ラグジュアリーと救済はなぜ“連続する”のか
寺社仏閣や教会といった宗教空間は、
人を救済へ導くために光・音・香り・静寂・秩序を用いてきた。
これはラグジュアリーが扱う“上質な感覚”と同じ構造である。
つまり、
上質な感覚体験(構造)
↓ゆとりの開花(心理作用)
↓救済として働く(存在論的作用)
という三段階の連続は、
宗教空間にも茶室にも、そして現代のラグジュアリー空間にも共通している。
では、茶室には神がいたのか?
答えは、いない。
それでも救済として機能していた。
この視点から見れば、日本におけるラグジュアリーは、
“神不在の救済”の感覚体験だと理解できるのではないだろうか。
【終章】上質の核心へ
ここまで整理すると、3語の違いは明確である。
プレミアム:ランクの概念
ゴージャス:派手さの概念
ラグジュアリー:上質な感覚体験の概念
そしてラグジュアリーだけが、
体験者の素地に依存し、
ゆとりを必要とし、
上質な感覚として体験者の中で立ち上がり、
ときに救済として働くこともある。
上質とは、物の値段ではなく 体験の構造 に宿る。
ラグジュアリーとは何か──
それは、
上質な感覚体験が、人の中に“小さなゆとり”を生み、
ときにそれが救済として働く現象である。
プレミアムやゴージャスでは決してたどりつけない、
人間の深層に触れる価値がここにある。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ