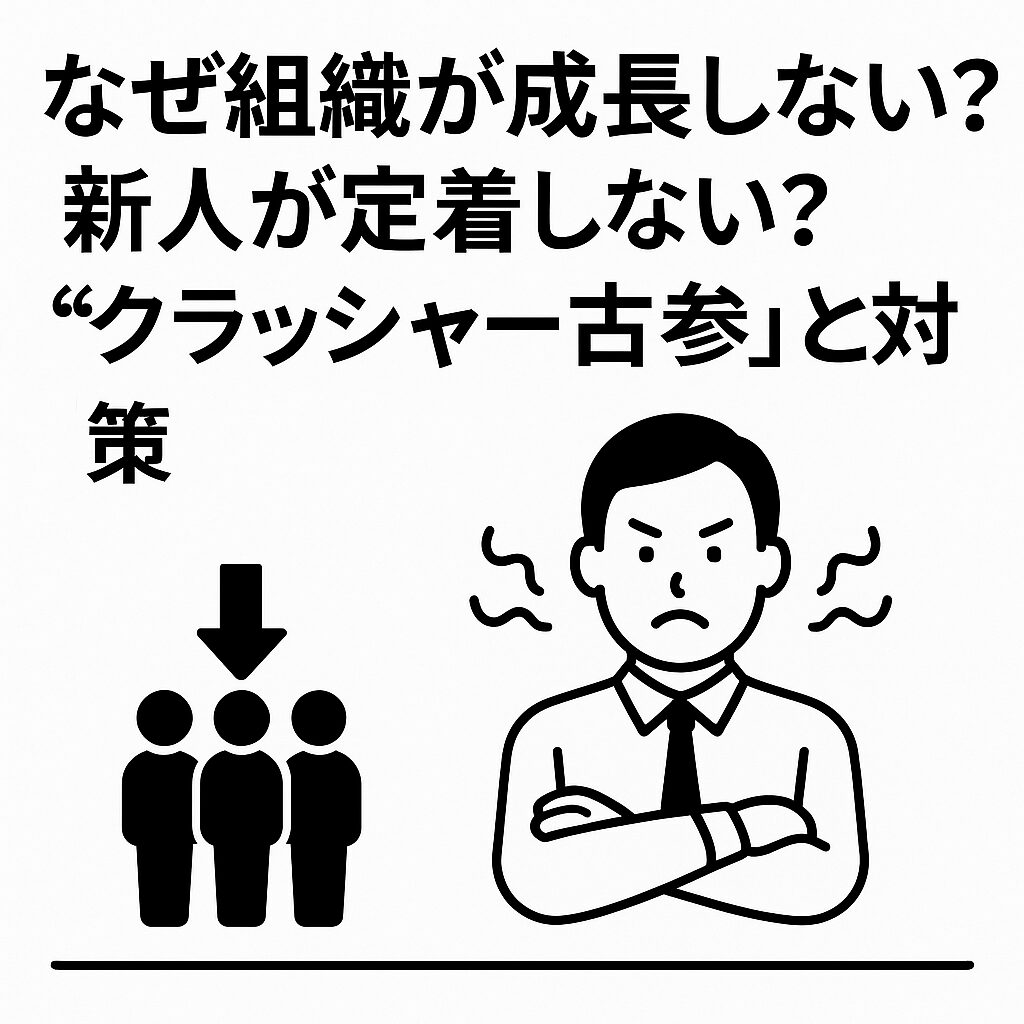Contents
序章:業績は悪くないのに、なぜか伸びない組織
毎年そこそこの利益を出していて、経営は安定している。
しかし、事業規模も人材の層もまったく広がらない。
そんな「成長しない組織」は、決して珍しくありません。
原因は市場や景気ではなく、職場内部の構造的な停滞にあります。
その中心には、組織の空気を支配する「古参職員」がいる。
彼らは長年の経験を盾に、無意識のうちに変化を拒み続けています。
第1章:成長を止める古参職員の行動パターン
成長を妨げる古参職員の行動には、一定の共通項があります。
以下に典型的な例を挙げましょう。
不熱心だが、熱心なフリだけは上手い。
「指導」と称して新人をいじめる。
自分の業務を後輩に押し付け、責任だけは取らない。
勤続年数を特権化し、発言権を独占する。
組織ルールを軽視し、「俺はこうやってきた」で済ませる。
感情のままに叱責し、報連相に主観を混ぜて問題を曖昧にする。
上には媚び、下には威圧的。
事務室の端から大声で人を呼びつけ、職場全体を支配する。
こうした人物の多くは、他社経験のないプロパー職員です。
外部の常識や多様な価値観に触れたことがないため、
「自分のやり方=正解」という確信を持ち、組織を硬直化させます。
その結果、職場は**声の大きい者が強い“閉鎖空間”**となり、
新人や外部人材は早々に離れていきます。
第2章:新人が定着しない本当の理由 ― “クラッシャー”の存在
新人が次々と辞めていく職場の裏には、
しばしば「クラッシャー」と呼ばれる存在がいます。
クラッシャーとは、部下や後輩に過剰なストレスを与え、
職場を静かに破壊していく人のこと。
表面上は「指導熱心」でも、実際には相手の成長を阻む言動を繰り返します。
特に優秀な新人ほど、こうした環境を敏感に察知し、早々に退職します。
そして残るのは、現状を疑わない人だけ。
このスパイラルが続くと、組織は**“安定しているように見えて、実は劣化している”状態**になります。
第3章:クラッシャーを特定するには ― 職場の可視化
クラッシャーの特定に有効なのが、
**「相互評価アンケート」**によるストレス構造の可視化です。
仕組み:社員が匿名で同僚を評価し、誰がストレス源となっているかを明らかにする。
(評価する側は匿名、評価される側は実名)特徴:複数の社員から同一人物が挙がれば、クラッシャーの可能性が高い。
ただし、運用には慎重な配慮が必要です。
匿名性を徹底:誰が評価したか推測できない設計にする。
外部専門家の関与:産業医や調査専門家に依頼し、公平性を確保。
質問の簡明化:数値評価で回答しやすい形式に。
重要なのは、告発ではなく構造の理解を目的とすること。
クラッシャー問題は個人攻撃ではなく、行動パターンの偏りとして捉えるべきです。
第4章:職場を立て直すための具体策
クラッシャーを特定したあとは、排除ではなく「行動変容」を促します。
リーダーシップ研修の実施
クラッシャーに「叱責ではなく育成」を学ぶ機会を与える。コミュニケーションの再設計
誰でも意見を出せる場を作り、発言の独占を防ぐ。経営層の明確な姿勢
トップがこの問題を「組織課題」として明言し、再発防止を指揮する。
指導の目的は「あなたが悪い」と責めることではない。
「そのやり方は、もう時代に合っていない」と伝えることです。
これにより、古参職員も“自分の居場所を守るための変化”を受け入れやすくなります。
第5章:放置の代償と再生の条件
クラッシャーを放置すれば、新人は次々と辞めます。
採用や研修コストが無駄になるだけでなく、
残った職員の士気まで下がり、組織文化そのものが荒廃していきます。
直属上司の「理解しているのに動けない」構造的限界
では、なぜ多くの組織で「クラッシャー放置」が繰り返されるのでしょうか。
その理由は単純な怠慢ではなく、直属上司の構造的な限界にあります。
多くの上司は、現場の問題を認識しています。
しかし彼ら自身が、抽象度の高いマネジメント業務――
たとえば部署間調整、数値目標の達成、人事考課など――に日々追われ、
クラッシャー個人への対応に割く時間も心理的余裕もないのです。
このように、**「理解しているのに手を打てない上司」**が量産され、
結果として問題職員が長期的に温存される構造が生まれます。
だからこそ、クラッシャー問題の解決には、
外部の専門家による同定と評価が欠かせません。
外部の視点は、内部の力関係や既得権益に左右されません。
産業医、社会調査の専門家、心理職など第三者が関与することで、
「誰が職場ストレスの起点になっているか」を客観的に明らかにできるのです。
こうした客観的データが、上司にとっての“行動トリガー”となり、
「分かってはいるが動けない」状態を打破する起点になります。
行動基準の再定義へ
再生の第一歩は、行動基準の再定義です。
声の大きさではなく成果で評価する。
勤続年数ではなく成長意欲を重視する。
感情ではなくデータと対話で判断する。
この3点を徹底するだけで、職場の空気は驚くほど変わります。
古参が変わらなくても、ルールが変われば行動は変わるのです。
結章:成長しない組織は“酸欠の温室”
収益性は「まあまあ」でも、変化を拒めばやがて酸欠になります。
外からの新しい風を入れなければ、内部で呼吸ができなくなるのです。
組織を再生させる鍵は、
古参を責めることでも、新人を守ることでもなく、
構造を見抜き、ルールを再設計できる上司の存在です。
クラッシャーは“悪人”ではなく、“時代に取り残された人”。
だからこそ、排除よりも再接続。
それが、職場を再び息づかせる唯一の道なのです。