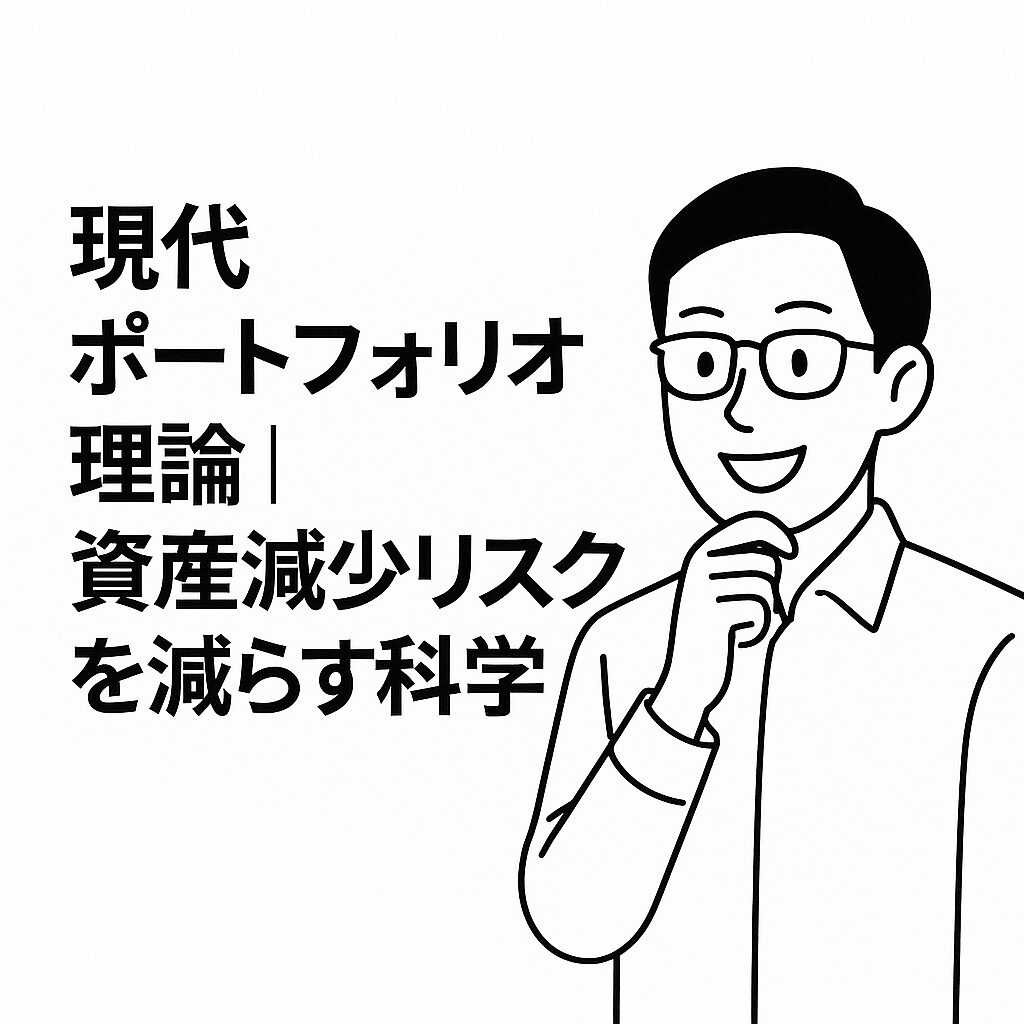Contents
■ はじめに
現代ポートフォリオ理論(MPT:Modern Portfolio Theory)は、
ハリー・マーコヴィッツによって提唱され、1990年にノーベル経済学賞を受賞した、金融理論の中核に位置する理論である。
この理論の核心は、
複数の資産を組み合わせることで、全体としての資産減少リスクを減らせる
という事実を数学的に証明した点にある。
これは経験則ではなく “科学として確立した法則” であり、
資産形成を考えるうえで避けて通れない基盤になる。
本稿では、難しい数式には踏み込まず、
この理論から導かれる“含意”だけに焦点を当てる。
ここで扱うリスクは、本来のボラティリティ概念を離れ、
“資産減少の可能性” として統一的に扱うことにする。
■ 第1章 現代ポートフォリオ理論とは何か
MPTが証明したもっとも重要な事実は、次の一点に尽きる。
異なる価格変動する複数の資産を組み合わせれば、全体の資産価値減少リスクを下げられる。
合理的な分散投資とは、
“たくさんの銘柄を持つこと” でも
“地域を広げること” でもなく、
揺れ方の違う資産を組み合わせること
なのである。
■ 第2章 なぜ資産を組み合わせるとリスクを減らせるのか
株式・債券・不動産・コモディティなどの資産クラスは、
それぞれ “異なる要因” によって価格が変動する。
株式:企業利益・景気・金利
債券:金利・信用リスク
不動産:賃料・金利・地域需給
コモディティ:天候・供給ショック・地政学
金:安全資産需要・通貨不信
揺れる理由が違うため、
これらは同方向に同じ強さで動きにくい。
この「揺れ方の違い(相関の低さ)」こそが、資産減少リスクを抑える源泉である。
逆に言えば、
揺れ方が同じものを増やしても分散にはならない。
■ 第3章 効率的フロンティア──最適な組み合わせが存在する
現代ポートフォリオ理論が導く帰結として、
効率的フロンティア(Efficient Frontier) という概念がある。
これは、
同じリスクならもっともリターンの高い組み合わせ
同じリターンならもっともリスクの低い組み合わせ
が数学的に存在する、というものだ。
この“最適点”は、
勘や経験で到達することはできず、
数学によってはじめて輪郭が見える。
銘柄数を増やすことではなく、
異なる揺れ方の資産をどう組み合わせるか
が本質になる。
■ 第4章 現代ポートフォリオ理論が示す含意
ここから、MPTが教えてくれる“実践的な含意”を整理する。
含意①:似たような個別株を複数持っていてもリスクはあまり減らない
複数銘柄を保有するとリスクが減る…というのは誤解されやすい点だ。
「トヨタ・ホンダ・日産を持っている」
「食品株を10銘柄」
「高配当株を20銘柄」
一見して分散されているように見えるが、
いずれも 動く理由が同じ ため、相関が高い。
“国内株という一つのカゴ”に入った卵の種類を変えているだけで、資産減少リスクはほとんど下がらない。
銘柄数ではなく、揺れ方の違い が分散の核心である。
含意②:先進国株 × 新興国株は“分散投資”ではない
一般には「地域を分散させよう」と言われるが、
実証データでは 先進国株と新興国株の相関は0.7〜0.9 と非常に高い。
金利ショック
世界景気の悪化
リスクオフの資金逃避
これらの要因は先進国と新興国を同時に揺らすため、
“下がるときは一緒に下がる”。
また新興国は、
市場データの歴史が短く価格変動の評価が不正確
政治・法制度の不連続リスク:カントリーリスク
通貨価値の急落
資本規制
信頼性の低いデータ:統計情報の信頼性が低いケースも
といった “構造的リスク” を抱える。
それにもかかわらず、
先進国株と同じ方向へ動いてしまうため、
分散先としての合理性は理論的にも実証的にもきわめて低い。
含意③:日本・米国・欧州など先進国同士も分散効果は限定的
「国を分ければ分散になる」というのも誤りだ。
日本・米国・欧州株の相関は 0.6〜0.9 に収束する。
理由は、
世界景気
グローバル金利(ドル金利)
リスクオン・リスクオフの潮流
国際資本移動の一体化
といった共通要因で同方向に動くためである。
つまり、
国の数を増やしても、揺れの根源が同じなら分散にはならない。
含意④:相関の低い組み合わせのみが「本物の分散」をつくる
では、何を組み合わせればよいのか。
実証と理論が一致して“相関が低い(または負の相関)”と確認されている組み合わせは、以下の3つだけである。
株式 × 債券(最強)
株式 × 金(相関が最も低い)
株式 × コモディティ(揺れの理由が根本的に株と異なる)
これらは“揺れ方の理由”が明確に違うため、
ポートフォリオ全体の資産減少リスクを下げる効果が安定して確認されている。
含意⑤:最終的に“市場全体を買う”という結論がもっとも合理的になる
効率的フロンティアを自力で構築することは、
プロでも簡単ではない。
そのため、数学的には
市場全体(インデックス)を買うことが
最適解にもっとも近い。
これは経験則ではなく、
現代ポートフォリオ理論に近似するための最も簡単な方法である事が分かっている。
■ 第5章 資産形成への実務的示唆
現代ポートフォリオ理論から導かれる示唆は極めて実践的だ。
● 実務的示唆①:銘柄数を増やすより、揺れ方の違いを増やす
多くの個別株を持ってもリスクは減らない。
“相関の低い資産”を混ぜることが、唯一の正攻法である。
● 実務的示唆②:分散はジャンルや地域ではなく“揺れ方”で判断する
世界中の株を集めたつもりでも、
揺れ方が同じなら意味がない。
分散とは「数」ではなく「動き方」である。
● 実務的示唆③:最も再現性が高い戦略は“市場全体を買う”
個人が効率的フロンティアを目指すのは困難。
市場全体を買うインデックス投資が、もっとも再現性の高い合理的戦略となる。
■ 結び
現代ポートフォリオ理論は、
不確実性の中で自分の未来を守るための“意思決定の科学”である。
資産減少リスクを抑える
安定と成長を両立させる
選択肢を複数確保する
これらを数学的に体系化し、
“分散とは何か” を最も正確に定義した理論がMPTである。
数式の細部を知らなくても、
この理論の“含意”だけ理解すれば、
資産形成の方針は劇的に明晰になる。
不確実な人生において、
強く、柔らかく、賢く生きるための道標として
現代ポートフォリオ理論ほど頼りになる理論はない。
当サイト内の他記事へは下記から
資産形成についての記事一覧
当サイト内記事のトピック一覧ページ 【最上位のページ】
筆者紹介は理屈コネ太郎の知ったか自慢|35歳で医師となり定年後は趣味と学びに邁進中