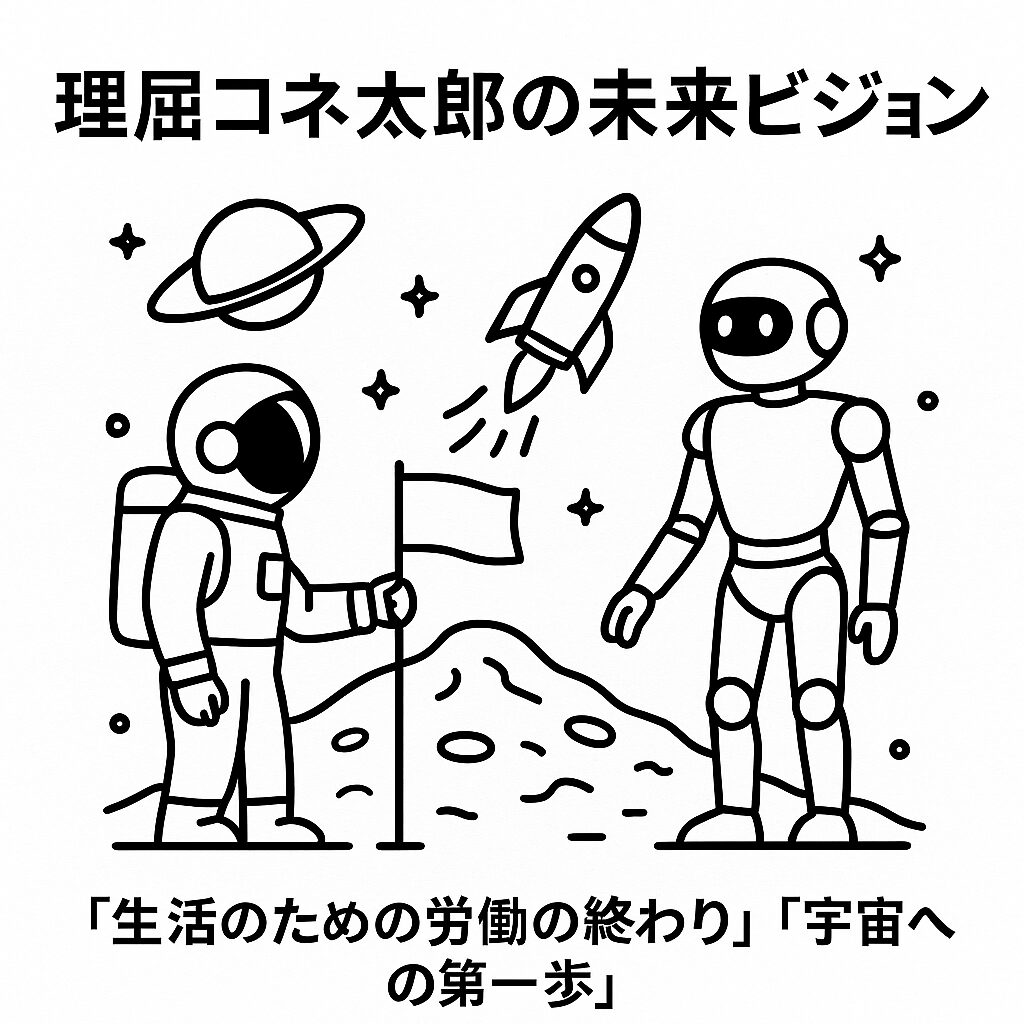技術の普及が富やお金の意味を減少させる。そんな予測を理屈コネ太郎はしています。これまでの人類史・文明史・産業史・技術史を俯瞰したうえでの予測ですが、理屈コネ太郎個人の管見内での私見に過ぎません。こんな考え方もあるのだなぁ…くらいの気持ちで読み進めて頂ければ幸いです。
Contents
■序章:科学技術の歴史は、“労働の削減”の歴史でもあった
科学技術の歴史を振り返ると、その発展は常に、生活の基盤を底上げし、労働の負荷を軽減する方向に社会に作用してきた。
蒸気機関は肉体労働を軽くし、洗濯機は家事の負担を減らし、冷蔵庫は食料管理の不安を取り除いた。
ファックス・メール・パソコンといった通信技術は、かつて膨大な時間を奪っていた“地味で細かな事務労働”を高速処理し、下水道や浄水施設は都市の衛生環境を大きく改善し、人々の暮らしを衛生的で安定したものに変えた。
これまで人類は、生きるために労働してきた。
ある者は給与として、ある者は現物支給として労働の対価を受け取り、その“労働の成果”で衣食住を賄ってきた。これがこれまでの人類における労働の意味だった。
この「働かないと生きられない」という構造が、これまでの人類史のほぼすべてを基底的な事実として支配してきた。
しかし、AIとロボティクスの急激な発展は、この“歴史の前提”そのものを揺るがし始めている。ここ数年のAIやロボの進歩には目を見張るものがある。その恩恵に触れた人ならば、AI搭載の高性能汎用ロボットが近い将来現実になることを強い確信をもって想像できるはずだ。
理屈コネ太郎自身も、その確信を抱いている。
本記事は、こうしたロボットの登場が人類の生活と価値観──特に“富の意味”をどう変え、働かなくても文化的に生活できる社会が、社会保障ではなく技術そのもので実現しうるという未来像を、理屈コネ太郎の想像力で描出してみたい。
■1. 生活のための労働は、すべてAI搭載ロボが引き受ける
高性能汎用ロボは、料理・掃除・買い物・運転・家のメンテナンスまで、人間が面倒くさいと感じる作業、やりたくない作業の全てを担当する時代になる。
そして、もしあなたが
「さっきまで回遊していたマグロ食べたいから獲って来て」
と指示すれば、ロボはそのまま海に入り、回遊データを参照しながらマグロを探知し捕獲し、その場で適切に魚を締め、血抜きを行い、最良の状態でクーラーボックスに収めて帰ってくる。
これはもはや「ぜいたくなサービス」ではなく、人間の代わりに生活の糧を獲得する存在であり、日々の生活のデフォルト装備である。
■2. ほとんどの人が“生活に必要な以上”の快適さを得られる
AI搭載高性能汎用ロボが実現する生活は、所有者の想像力を反映して生活の質は高く、安定している。
食糧を獲ってきて調理する
常に居住空間を快適に保つ
一緒に富士山に登り、人間が疲れたら背負って登頂する
帰路では人間はお姫様抱っこで眠りにつき、ロボが自分の判断で下山する
各種トラブルの自動検知と自動処理
かつて富裕層だけが対価を大勢の人間に支払う事で享受できた生活水準が、ロボの普及によって“ほぼ全員の標準”になる。
技術は人類の生活の“最低ライン”を底上げする力を持つ。
その力が今、歴史的規模で作用し始めている。
■3. 殆どの労働は、人間よりロボが上手にこなす
ロボットは反復労働にも強く、集中力が切れることもない。
個人の生活をサポートする以外にも、産業の現場では、人体ではとうてい不可能な作業を、人間ではとうてい堪えられない環境下で長時間実行できる。
ロボットは適切なメンテナンスさえすれば、人間よりあらゆる環境につよく、長時間は働ける。夜間でも照明なしで高度な作業を行える。レアアースの精製や濃縮にだって耐えられるし、高放射線下での労働も平気だ。
個人の生活場面だけでなく、産業のあらゆる階層と分野でAI搭載ロボットは労働する。
この状態ではもはや、「ロボットに人間の仕事が奪われる」というような生易しい状況ではない。生活サポートロボットや産業ロボットのおかげで、人間は本当の意味で生活のために労働する必要性がなくなる。生活のための義務的で高負荷で面倒な労働から人間が解放される…ということ。
働かざるもの食うべからず‥の格言は消失し、働く必要性が全くなくなる世界になる。
要するに、生活も産業も、人間を“労働力として”必要としない世界が到来する。だから人間は、「働かざるを得ない存在」から「働いてもよい存在」へと立場を変える。
■4. 労働が消えることで、お金の意味も縮小していく
富とは本来、自分がやりたくない仕事を、他の誰かに代わりにやってもらうためのツールである。
だから富を多く持つ者は、自分がやりたくない労働を多数の人にかわりにやってもらっていた。
しかしロボがそれを“無料で、しかも人間以上の精度で長時間こなしてしまう”社会では、富は生活の質を左右する主要要素ではなくなる。
なぜなら、人間が対価を受け取って引き受ける労働が蒸発し、消失してしまうからだ。これまで対価を支払って他の誰かに引き受けてもらっていた労働は全て、AI搭載高性能汎用ロボにやってもらえばいい。
排水溝の掃除も、高所の作業も、船底の掃除も、ヨットのマストに上っての作業も、ゴキブリの駆除も、ちょっとでも怖かったり嫌だったりする労働はすべてロボットにやってもらう。
生きるための安心と快適は、お金とは無関係に得られるようになる。
■5. お金は希少品の購入に使われるだけになる
富、つまりお金は美術品や骨とう品、歴史的な物品などの購入に用いられるしか使いようがなくなるが、古い品物は劣化対策が大変であり、個人所有には馴染まない。
温度や湿度が管理された博物館で保管されるのが、コスト的にもセキュリティー的にも、また美術愛好家の心理からしても、もっとも負荷がすくない。そうすると、そこでも富、つまりお金の意義は薄くなる。
■6. 「やりたくない仕事」はすべてロボが担当する
人間の仕事には三種類がある。
やりたい仕事
やってもよい仕事
やりたくない仕事
“やりたくない仕事”は完全にロボが担当し、“やってもよい仕事”でもロボの方が効率的になる。結果、人間に残るのは “やりたいことをやる”という選択肢だけ である。
すこし話しはわきにそれるが、AI搭載高性能汎用型ロボットが社会実装される社会では、恐らく出生率は下がるだろう。個人のイマジネーションやクリエティビティーを、ロボを使って実現できる時代には、もはやロマンスは人類にとって魅力的な感情ではなくなると思われるから。
そして人類の総数は減少する。
■7. 地球上の探査と開発はロボが完全に担う
そこで、やりたい事だけに全ての注意力と時間を注げる希少種である人類は、地球と人間の理解へとまずは突き進むだろう。海底にはステーションが整備され、深海探査も資源調査も地殻観察もロボが行う。
砂漠、極地、火山帯、ジャングルなど、人間には危険な領域もロボが安全に調査する。
また人間の心身についての探求も極められる。血管内内視鏡が実現し、動脈硬化を局所的に診断し治療する。それもAIの診断と判断と手技によって。
思想の世界でも、膨大な数の哲学者や思想家のテキストが解釈され、簡明な言葉で同じ内容が表現できるようになった結果、
「複雑な現象を簡明に説明しようとした人」
「複雑なことを別の複雑な言葉で説明しようとした人」
「実際は空虚な内容を難解な用語で哲学風・思想風に見せていた人」
こうした区別が、かなりはっきりしてくるだろう。
心理学は脳の構造や機能の研究と、リアルタイムで起きている社会現象の解析が統合され、さまざまな要素を抽出して関連付け、法則性を見つけ出せるようになる。
地球と人間の“未知部分”は急速に減り、「ほぼ理解できた」と人類が認知する時がくるだろう。
この星の出来事は全て観察された……と。
その時、人類の探求心はどこに向かうだろう。それはもう宇宙しかない。ここでいう宇宙とは、地球の衛星軌道程度のことではなく、他の天体、太陽系の果ての惑星、そして別の太陽系へと向かうことだ。
労働の自動化が完成した事で富の価値がほぼ消滅し、人間の数が減少して希少種となり、そして興味の対象が宇宙へと向かうとしたら、人類はおそらく宇宙艦隊を創設するだろう。そして、その艦隊に属する船には エンタープライズ という船名をあたえるかも知れない。
だがエンタープライズは脅威に対抗するための武装は持っているが、戦艦ではない。地球と人類を極めた…と人間が考えたときに、宇宙での新しい知見を広めるための船が戦艦であるはずがない。
■8. 人類は最後のフロンティアを宇宙に求める
生活の不安がなく、地球上の探査もロボが完了すると、人類の視線は自然と宇宙へ向かう。
希少種と自覚した人類は、富でも義務でもなく、ひたすらに自分のやりたい事をやり抜くために生きるようになる。
■9. 資本主義的思考からの解放
人類は「生きるために労働する」必要から完全に自由になる。
労働は義務ではなく、自分の目的と好奇心のために行う行動となり、競争や富の追求は文明の中心ではなくなる。
■10. 宇宙艦隊が組織され、外宇宙探査が始まる
生活の基盤はロボが完璧に支え、地球上の探査は終わり、希少種である人類は宇宙へ向かう準備を整える。
宇宙艦隊は深宇宙探査を目的に組織され、人類とロボは“旅の仲間”としてともに外宇宙へ向かう。
そのとき価値を持つのは、富でも地位でもなく、知りたい・確かめたい・試したいという人間本来の動機である。
■おわりに
これは空想ではあるけれど、理屈コネ太郎が、伴走するAIとの会話から描き出した人類の未来である。
蒸気機関から電子通信、そしてAIとロボットへ。
技術の流れは一貫して、“生活のための義務的で面倒な労働”から人を解放する方向へ進んできた。
その延長線上で、人類は やりたいことをして生きる社会 へ移行し、次の物語を宇宙に求めるようになる。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ