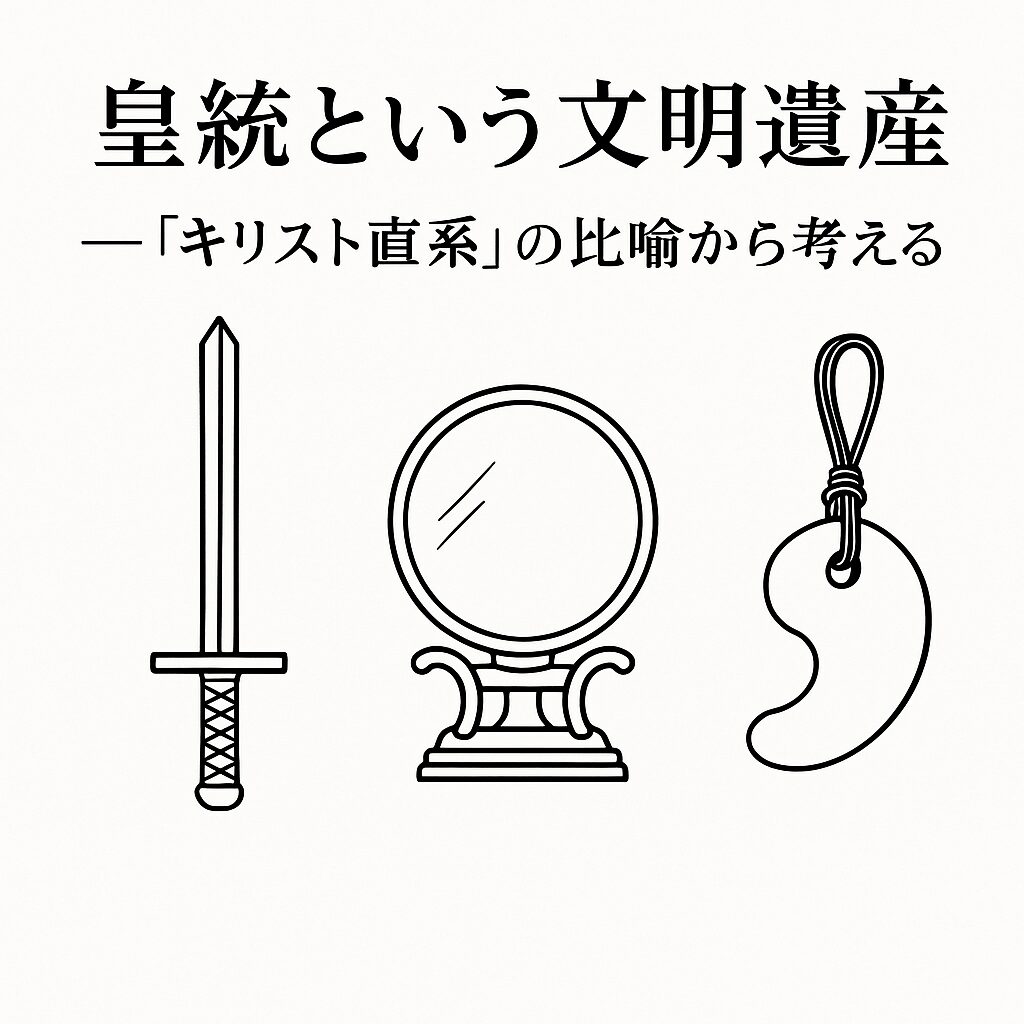Contents
1.本記事は愛国論ではありません
最初に断っておきたいのは、この文章は「日本すごい!」を叫ぶ愛国記事ではないということ。
私は日本人として皇統に親近感と敬意を抱いている。
しかし、本記事で扱いたいのは日本文化を誇ることではなく、
「もし私が欧州人だったら、この皇統をどう眺めただろうか?」
という人類史・文明史的な俯瞰の視点である。
日本だから擁護する──ではない。
私は今、たまたま日本に生まれた者としてではなく、
文明を観察する“外側の視線” で皇統を理解しようとしている。
そこから見えてくるものは、
愛国感情ではなく、
文明としての稀少性
時間が生むラグジュアリー
人類史の棚に並べたときの“一点もの”としての価値
である。
そうした視点から見ると、
皇統とは「日本だけが誇るもの」ではなく、
世界の文明史の中でも数少ない、
他に替えのきかない“一点もの”として位置づけられる存在である。
2.キリスト教文明への敬意
タイトルが示す通り本記事では皇統理解のためにキリスト教を例として用いるが、その前にまず、キリスト教文明へ寄せる敬意について明言しておきたい。
ヨーロッパの近代科学、制度思想、産業革命──
その精神的母体がキリスト教世界にあったことは疑いようがない。
世界は神の創造した秩序ある構造
であれば理性によって理解可能である
この確信は、
自然法則、合理主義、学問体系の成立に大きく寄与した。
そしてキリスト教は、人間の内側にも大きな仕事をした。
良心
罪との向き合い
内省
他者への責任
という「内なる問い」を、社会の深部に根づかせた文明である。
さらに重要なことがある。
キリスト教の教義継承において“血統”は本質的価値を持たない。
イエスは「神の子」であっても、イエスの血筋そのものは救済の条件ではない。
“信じる共同体”こそが核であり、
血統が教義継承の中心になることはほとんどなかった。
この前提が、これからの思考実験を理解する上で重要である。
3.思考実験:キリスト直系子孫が“代々生きる国”
ここで、ひとつ思考実験としての想像をしてみて欲しい。
これはあくまで比喩であり、歴史的事実を主張するものではない。
イエス・キリストの直系の子孫が“代々生きる国”が、
地中海の東の沿岸に存在しているとしたら──。
その血統が、
十字軍
宗教改革
王朝交代
世界大戦
政体の激変
といった歴史をすべて耐え抜き、
いまもなお静かに連綿と在り続けているとしたら。
その国を見たとき、
キリスト教文明圏の人々はどれほど深く揺さぶられるだろうか。
畏怖
敬意
驚嘆
歴史の重みに対する感覚の反転
さまざまな感情が渦を巻くだろう。
4.その比喩にもっとも似た構造をもつ文明が、日本である
私は、
この比喩にもっとも似た歴史構造をもっている文明が、
じつは日本であると考えている。
誤解しないで欲しい。
天皇がキリストの血筋だと言いたいわけではない
日本が優れていると言いたいのでもない
神話を歴史と混同するつもりもない
そうではなく、
欧州人が“キリスト直系子孫が連綿と続く国”に抱くであろう直感的センセーションに、日本の皇統の希少性や価値、意味が端的に凝縮されている。
それがここで伝えたい核である。
5.天皇は「創造主」ではない。しかし日本の“唯一の不変の軸”であった
天皇は創造主ではない。
しかし、“日本という物語の連続性”を体現する唯一の存在である。
日本では、
政権は武家に変わり
幕府が興り
明治政府が成立し
戦後民主主義へと移行した
しかしその背後で、
皇統だけはただひたすら続き続けた。
この構造は文明史・人類史・世界史的に極めて稀有である。
もしわたし理屈コネ太郎が欧州人だったなら、
キリスト教よりも長く続くこの皇統を、
人類史・文明史の尺度で見ても極めて貴重な歴史的価値として捉えたはずだろう。そして、その改編は「一国の制度変更」ではなく、
人類が共有する文化・文明の価値の一部を失う行為として映るに違いない。
これは愛国感情ではなく、
文明を愛する者の自然な審美眼である。
6.無常の国で、皇統は“唯一変わらない軸”だったのではないか
日本は世界でも珍しい「無常の国」である。平家物語の冒頭、諸行無常の響きありと謳われ、方丈記にはかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例なし。良寛は、散る桜、残る桜も散る桜、と言った。
大地震
大津波
台風
洪水
噴火
数十年単位で大きな天変地異が起こり、
町は焼け、村は流され、家は倒壊した。
だから日本の住まいは石ではなく、
“壊れること”を前提にした木と紙
で作るようになった。
石造の殿堂を建てても、次の災害で倒れる。
ならば軽く、しなやかで、すぐに建て直せる構造の方が合理的である。
しかし、
この“すべてが壊れる国”の中で、
ただひとつだけ壊れなかったものがある。
それが皇統である。
すべてが移ろう国だからこそ、
唯一変わらない軸の存在は、
人々にとって心の支えになったはずだ。
家は壊れる、街は焼ける、国の秩序も変わる──
しかし、天皇だけは必ずそこにいる。
この“静かな不変性”が、
災厄にさらされ続ける日本人の精神性の奥深くで
どれほど大きな意味を持ってきたか想像に難くない。
さらに象徴的なのが「民のかまど」伝説である。
天皇が「民の竈(かまど)」の煙を心配する──
これは欧州の王権や教会ではまず発想されない物語だ。
災害と復興のサイクルを生きる国において、
為政者ではなく“見守る象徴”としての君主像が発達した結果である。
皇統は、日本人の精神性にとって小さな存在ではなかった。
もし“小さく見える”のだとすれば、
その多くは戦後のGHQによる歴史観の書き換えによるものだろう。
本来の皇統は、
制度や政治を超えた「文化の深層」に根づいていた。
7.皇統という文明のラグジュアリー
皇統は、政治制度ではない。
むしろ文明史の棚に並べるべき“唯一性の文化遺産”である。
ラグジュアリーとは本来、
模倣不能
再生産不能
時間が価値そのものになっているもの
を指す。
その意味で皇統は、
文明としてのラグジュアリーの極致である。
一度失えば、
二度と戻らない。
歴史的な重層性によるラグジュアリーは大変に貴重なブランドたりえる。
8.たまたまこの文明に生まれたという、静かな悦び
私は日本人として皇統を敬うが、
それ以上に、
もし私が欧州人だったとしても、
この連続王統を“人類史のミラクル”として深く敬意を抱いただろう。
それほどまでに、
皇統は世界史の中で唯一性の高い存在だ。
それを声高に誇る必要はない。
他の文化文明と競い合う必要もない。
ただ、
2600年の連続性が当たり前に背景にあるという事実は、
静かに噛みしめるべき贅沢だと思っている。
それは政治の話ではなく、
文化と文明の歴史の話なのだ。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ