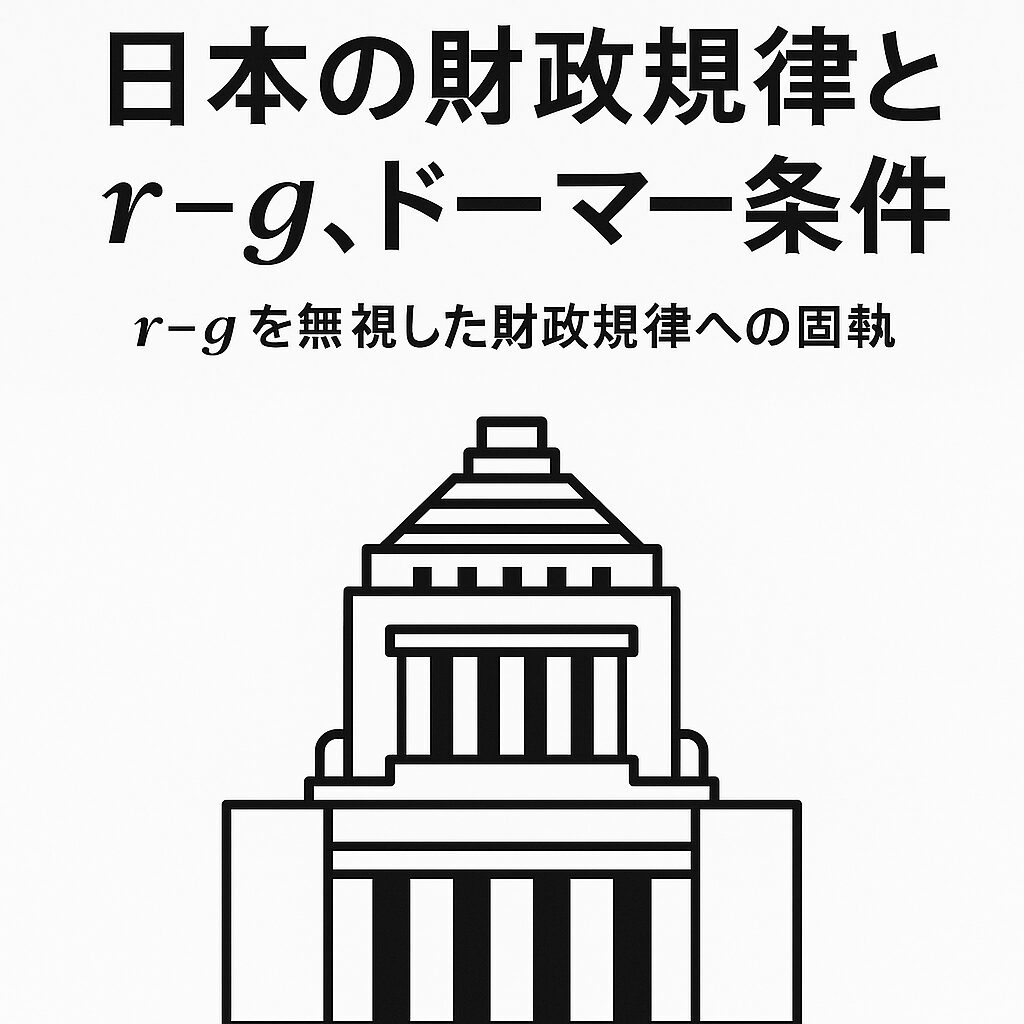Contents
良くならない景気と上がらない給料
日本の経済が停滞したこの30年を理屈コネ太郎的に分析し、停滞の理由を解決策を管見内の私見として述べたいと思います。かなりの力作です。お愉しみ下さい。
日本の財政政策は、戦後から現在に至るまで、帳簿上の均衡を重視してきた。
しかし、財政の健全性は赤字の有無ではなく、赤字を補うために発行する国債の金利よりも経済の伸びが上回る状態をどれだけ維持できるかで判断されるべきである。
経済が拡大すれば、債務の対GDP比は自然に低下する。逆に、成長が停滞したまま支出を削減しても、債務比率は改善しない。
それにもかかわらず、日本政府は長期にわたり、財政の帳尻を合わせることを目的化してきた。
この「静的均衡」の発想は、1949年のジョゼフ・M・ドッジによるドッジ・ラインに始まる。
ハイパーインフレを抑制するために導入されたこの政策は、短期的には物価を安定させたが、同時に「財政赤字=不健全」という価値観を制度化した。
以降、財政当局はインフレ抑制を国家の基本方針とし、経済成長よりも均衡財政を優先する政策文化を形成した。
この文化は、オイルショック、バブル崩壊、平成デフレ、そしてコロナ禍に至るまで一貫して維持された。
経済が停滞するたびに日本政府は支出拡大ではなく支出削減を選択し、均衡財政規範(Balanced Budget Norm)が政策判断の前提として機能してきた。
経済学では、政府の債務が長期的に持続可能かどうかを示す基本式として、ドーマー条件(Domar condition)が広く知られている。
それは次のように表される。
Δd=(r−g)×d−p
ここで、
:債務残高のGDP比、
:実質金利、
:経済成長率、
:プライマリーバランス(GDP比)
を意味する。
この式の核心は、r−g の符号が債務比率の方向を決めるという点にある。
r−g が正(=金利が成長より高い)なら債務比率は時間とともに増加し、
負(=成長が金利を上回る)なら債務比率は減少していく。
ドーマー条件の正しさは、財務省・財務総研の論文においても是認されている。それゆえ、現実の運用では国債需給などを式の“内側”に織り込もうと提案している程である(『フィナンシャル・レビュー』第145号)。
本稿では、戦後から令和までの日本の財政運営を、インフレ恐怖と均衡信仰の連鎖として検証する。
GHQ統治下から始まった「財政均衡ドグマ」が、どのようにして日本の政策判断を縛り、
経済危機のたびに誤った選択を繰り返させてきたのかを明らかにする。
分析の枠組みには、ドーマー条件と r−g の概念を用い、
「なぜ日本政府は成長よりも均衡を優先してきたのか」という問いに、経済史と思想の両面から答えを探る。
第1章 ドッジ・ラインと財政均衡信仰の誕生
1. 占領期の経済混乱と「通貨への恐怖」
1945年の敗戦後、日本経済は生産の崩壊とハイパーインフレに直面した。
軍需産業の急停止、復員・引揚げ者の流入、流通網の断絶が重なり、物価は数百倍に跳ね上がった。
政府は戦後復興の財源を確保するため、日銀引き受けによる国債発行に依存し、通貨量が急増。
円の信用は失われ、人々は物ではなく貨幣を避ける「モノ買い現象」に走った。
この経験が、日本における最初の「インフレ恐怖体験」となった。
のちに財務官僚たちはこの時期を「国家が通貨の信用を失った時代」と位置づけ、
「財政赤字=悪」「支出削減=健全」という倫理観を根付かせた。
2. ドッジの来日と「均衡財政」の導入
1949年、GHQの要請を受けて米国の銀行家ジョゼフ・M・ドッジが来日し、
彼の名を冠した経済安定化政策「ドッジ・ライン」を実施する。
目的は、通貨の信用回復と財政規律の確立だった。
ドッジは、政府支出の大幅削減、赤字国債の禁止、為替レートの固定(1ドル=360円)などを一体的に実施。
「企業再建の会計手法」を国家財政に適用したような政策だった。
短期的にはハイパーインフレを抑えたが、経済全体は急速に冷え込み、失業と倒産が拡大。
それでも政策は「成功」と評価され、均衡財政=健全経済という観念が制度として定着した。
3. 思想としての「静的均衡」
ドッジ・ラインは単なる財政改革ではなく、経済運営の哲学を変えた。
それまでの「復興と生産拡大」という動的目標が、「収支の均衡」という静的目標に置き換えられた。
この発想の転換が、のちの日本の大蔵省(現財務省)文化の出発点となる。
均衡財政の思想は、1950年代の池田勇人・佐藤栄作の官僚時代を通じて継承され、
やがて「財政規律を守ること」が官僚倫理そのものとなった。
この倫理は戦後日本の経済成長期にも維持され、
経済学的にはr<g状態が続き債務比率が低下していたにもかかわらず、
財政当局は依然として「赤字を恐れる文化」から脱しなかった。
4. 小結
1949年のドッジ・ラインは、日本の戦後財政の原型をつくった。
通貨安定という目的は達成されたが、その背後には「支出を減らすことこそ健全」という価値観が刷り込まれた。
以後、日本の財政思想は、経済のダイナミズムよりも会計上の整合性を優先する「静的均衡」へと傾いていく。
第2章 高度成長と実証された動学――理論なき成功(1955–1973)
1. 所得倍増計画と経済拡張の政策枠組み
1955年に自由民主党が結成され、政治の安定期が始まった。
1960年、池田勇人内閣は所得倍増計画を打ち出す。
その基本方針は「経済成長による国民生活の向上」であり、財政・金融・貿易政策を総動員する拡張戦略だった。
公共投資、社会資本整備、教育・研究開発支出が大幅に増加し、それが民間設備投資を誘発した。
名目GDPは1955年の約14兆円から1973年には約138兆円へと約10倍に拡大。
実質成長率は年平均9%を超え、同時期の金利水準(r)はそれを下回っていた。
債務の総額は増えたが、経済規模の拡大がそれを上回り、債務対GDP比(d)は低下。
政府支出の積極化にもかかわらず、財政は破綻しなかった。
2. ドーマー条件以前の実証――「理論なき健全財政」
この時期、マクロ経済学はまだ動学的な財政持続性の理論を体系化していなかった。
米国の経済学者エフゲニー・ドーマー(Evsey Domar)が
「The Burden of the Debt and the National Income」(1944)で示した式、
Δd=(r−g)×d−p
が国際的に注目され始めたのは1950年代後半以降である。
日本の政策形成にこの理論が直接影響を与えたわけではなかった。
それでも、池田勇人や佐藤栄作の政権下で実施された政策は、結果としてこの式の示す動学的関係を満たしていた。
すなわち、金利(r)が経済成長率(g)を下回る状態が長期間続き、債務比率は自然に低下していった。
当時の政府が「理論を理解していたから成功した」のではなく、経済の実態が理論を先取りしていたと言える。
3. 経済構造と成長のメカニズム
公共投資がインフラ整備と民間設備投資を連鎖的に拡大。
労働移動(農村から都市へ)と教育投資が人的資本を蓄積。
輸出主導型の外需が内需を押し上げ、産業構造が重化学工業中心へ転換。
技術革新と規模の経済が生産性を押し上げた。
こうして日本経済は高成長・低金利・低債務比率という安定的な均衡を形成した。
財政拡張がむしろ健全性を強化する——現代的にいえばr<g型の健全財政——を、
当時の日本は偶然ではなく構造的に実現していた。
4. 官僚機構の静的思考と「偶然説」
旧大蔵省(現財務省)には依然として、戦後ドッジ・ライン以来の「均衡財政」思想が根強く残っていた。
池田・佐藤政権期の成果は、彼らにとって「好景気による偶然の黒字」であり、
支出拡大が債務比率を下げたという動学的理解は共有されなかった。
この静的な財政観は、その後の政策転換期に影響を及ぼす。
5. 転機:1973年オイルショック
1973年、第一次オイルショックが発生した。
原油価格の急騰により輸入物価が上昇し、経済成長率(g)は大きく低下。
それでも金利(r)は下がらず、r−g は正転(r>g)へと変化した。
ここで本来必要だったのは、省エネ・技術革新への投資による成長率の回復(g↑)であり、
r<gを維持することで財政健全性を保つ戦略だった。
しかし政府と官僚機構は「インフレ抑制」を優先し、歳出削減と金融引き締めに転じた。
これにより、日本の財政運営は再び「静的均衡」に戻り、
高度成長期に偶然実現していた r<g 状態は失われていった。
6. 小結
1955〜1973年の日本経済は、理論的意識を伴わないまま、
のちにドーマー条件として定式化される「成長が債務を軽くする経済構造」を実際に実現していた。
財政が破綻しなかったのは偶然ではなく、r<g が長期間成立していた必然の帰結である。
しかし当時の政策担当者はそれを“均衡からの一時的逸脱”と見なし、
理論的理解を欠いたまま次の時代へ移行した。
その結果、1970年代後半以降、日本は再び「均衡の信仰」へ回帰していく。
第3章 オイルショックと再燃する「インフレ恐怖」(1973–1985)
1. 世界的供給ショックと日本経済の急減速
1973年秋、第四次中東戦争を契機に、OPEC諸国が原油価格を引き上げ、供給制限を実施した。
これが第一次オイルショックである。
原油価格は1バレル3ドル台から12ドル台へ急騰し、日本のエネルギー輸入依存経済は直撃を受けた。
エネルギーコストの上昇により、物価上昇率は1974年に23%に達した。
同時に、企業収益の悪化と生産調整で実質成長率はマイナス(−1.2%)へ転落。
これは戦後初のマイナス成長であり、「成長神話」が崩れた瞬間だった。
このとき、経済指標上では明確に
へと転じた。
金利は上昇し、成長率は低迷。
債務比率(d)は上昇に転じ、第二章で維持されていた「成長が債務を吸収する構造(r<g)」は終わりを告げた。
2. 政府の対応:物価抑制を最優先とした緊縮政策
当時の首相は田中角栄(〜1974年)から三木武夫、福田赳夫、大平正芳へと政権が移行した。
いずれの政権も共通して「インフレ退治」を最優先課題とした。
政府は総需要を抑えるために次の政策を実施した:
公共投資計画の削減(いわゆる「総需要抑制策」)
金融引き締め(公定歩合を1973年6.25%→9.0%へ引き上げ)
企業に対する価格・賃金抑制要請
この政策は短期的には物価の鎮静化に効果をもたらしたが、
同時に成長率(g)をさらに低下させ、r−g を拡大させる逆効果を生んだ。
3. 財政再建論の浮上と「赤字恐怖」の再来
1975年以降、景気低迷が原因の税収減により、国債発行が急増した。
この年、政府は戦後初めて「赤字国債」を発行する。
旧大蔵省はこれを「例外的措置」と位置づけたが、
メディアと世論は「財政赤字の時代が来た」と警鐘を鳴らした。
この時期、「赤字=不健全」「均衡=責任ある政治」という道徳的フレームが再び強化された。
財政再建論が政治課題として定着し、1980年の「財政再建元年」を迎える。
大平正芳内閣(1978–1980)は、経済成長よりも財政均衡を優先し、
国債依存を減らすための歳出抑制方針を明確にした。
彼の後を継いだ鈴木善幸内閣(1980–1982)は「増税なき財政再建」を掲げ、
歳出削減によって均衡を取り戻そうとした。
しかし、実際には成長率の低迷が続き、税収も伸びず、
r−g は依然として正のまま固定化。
債務比率は下がらず、再建は数字上の目標にとどまった。
4. 均衡ドグマの再定着と「静的思考」の制度化
この時期の政府と官僚の思考様式は、戦後直後のドッジ・ラインに極めて近い。
インフレを「過剰支出の結果」とみなし、財政出動の抑制を「健全化」と定義した。
しかし、実際のインフレは原材料価格の上昇による供給ショックであり、需要過多ではなかった。
にもかかわらず、政策は「需要抑制」を繰り返した。
結果として、実体経済の縮小が物価安定と引き換えに進行し、
日本は「安定成長」から「停滞成長」へ移行した。
この過程で「静的均衡」の考え方が制度として固定化された。
均衡財政を守ることが政策の目的そのものとなり、
成長率を高めて債務比率を下げるという動的均衡の発想は完全に失われた。
5. 第二次オイルショックと長期停滞の固定化
1979年、イラン革命をきっかけに原油価格が再び高騰。
これが第二次オイルショックである。
物価上昇が再燃し、金利は再び上昇。
r−g はさらに拡大し、債務比率の上昇に拍車がかかった。
鈴木善幸内閣下の大蔵省主導で歳出削減と金融引き締めが継続され、
1980年代初期の実質成長率は2〜3%台に低迷した。
高金利政策が続く中で、企業の設備投資は停滞し、
民間活力は次第に失われた。
一方、同時期の米国ではレーガン政権が積極財政による景気刺激策を実施し、
日本とは正反対の方向でr<gを取り戻そうとしていた。
この対照的な政策選択が、1980年代後半の国際構造に影響を与えることになる。
6. 小結
1970年代後半から1980年代前半にかけての日本は、
供給ショックを需要抑制で対応するという政策誤認を行った。
その結果、r−g が正の状態が続き、債務比率の上昇が止まらなかった。
それにもかかわらず、政策担当者は「支出削減=財政再建」と信じ、
経済の停滞を「安定」と呼んだ。
この時期に形成された「均衡=正義」という制度的信仰は、
のちにバブル期の金融・財政運営にも影響を与える。
次章では、1980年代後半のプラザ合意後の金融緩和と資産市場の過熱を経て、
再び「通貨の安定」を最優先する引き締め政策がどのように
バブル崩壊を招いたかを検証する。
第4章 バブル経済と「第二のドッジ・ライン」(1985–1995)
1. プラザ合意と円高不況
1985年9月、米・日・独・仏・英の5カ国はプラザ合意(Plaza Accord)に署名した。
目的は、過度なドル高を是正し、米国の貿易赤字を縮小することにあった。
各国は協調介入によってドル安・円高を進め、わずか1年で1ドル=240円から150円台へ。
輸出主導で成長してきた日本経済にとって、これは強烈な円高ショックとなった。
輸出企業は採算を失い、生産を減らし、国内景気は急速に悪化。
これがいわゆる「円高不況」である。
成長率(g)は鈍化し、企業の設備投資意欲も落ち込んだ。
2. 金融緩和と不動産・株式市場の過熱
円高不況を受け、当時の中曽根康弘内閣と竹下登蔵相のもとで、日本銀行は急速な金融緩和政策を実施した。
公定歩合は1985年の5.0%から1987年には2.5%へ引き下げられる。
この低金利政策により、市場には大量の資金が供給された。
しかし、企業の借入需要は弱かった。
円高で輸出採算が悪化し、国内で生産設備を拡張しても利益が出にくい状況にあった。
加えて企業は、将来の成長機会を国内よりも海外に求め、現地生産・現地調達へシフトしていた。
つまり、「国内で新しい設備をつくる理由が乏しかった」のである。
こうして企業が資金を借りない中で、行き場を失った銀行の資金は土地や株式市場へと流入した。
低金利による資産買いが連鎖し、株価と地価は急騰した。
日経平均株価:1985年 13,000円台 → 1989年末 38,915円
都心地価:1985年比で2〜3倍
この間、日本経済は短期的に r<g の状態を回復したが、
その「成長」は実体経済の拡大によるものではなく、不動産と株式だけが高騰した局地的なインフレだった。
つまり、経済全体で物価が上がっていたわけではない。
3. 政府が取るべきだった政策
もし政府が当時、円高の痛みを和らげ、国内企業の投資意欲を支える政策をとっていれば、
この資金は生産的な方向へ流れた可能性が高い。
具体的には、
技術革新や生産効率化への設備投資補助、
インフラ・住宅・都市再開発などの内需拡大型公共投資、
減税や研究開発支援による民間投資の誘発。
こうした政策で国内需要を確保すれば、企業の借入需要(投資需要)が戻り、
金融緩和の資金は資産市場ではなく実体経済に吸収されたはずである。
つまり、r<g を「実質的な経済成長による健全な均衡」として維持できた可能性があった。
4. 金融引き締めと不動産融資総量規制
物価(CPI)は安定していたが、政府と日本銀行は地価と株価の上昇をインフレと誤って認識した。
この誤診が政策転換を招く。
1989年5月から1990年8月にかけて、日銀は公定歩合を2.5%から6.0%へ引き上げ、急速な金融引き締めに転じた。
さらに大蔵省は、1990年3月に不動産融資総量規制を導入し、銀行の不動産向け貸出を一律に抑制した。
結果として資金供給が一気に縮小し、株価と地価は急落。
日経平均株価:1989年末 38,915円 → 1992年 14,000円台
地価:1991〜1993年にかけて40〜50%下落
本来なら、投機的な「含み益狙い」の案件だけを抑えるべきだったが、
総量規制は住宅・再開発・生産用不動産といった実需まで一律に冷やした。
融資が止まり、企業は資金繰りに窮し、建設・製造業にも波及。
バブルの過熱を抑えるどころか、実体経済ごと冷却させる結果となった。
5. 本来とるべきだった政策:税制による選別的冷却
不動産取引の利得構造にメスを入れる税制変更であれば、「悪い熱」だけを冷ますことが可能だった。
短期転売益への高課税:1〜2年以内の転売に高率課税を課し、投機を減らす。
固定資産税評価額の引き上げ:保有コストを上げ、土地の抱え込みを防ぐ。
不動産損益通算の制限:企業が財テク目的で土地売買を行う動機を弱める。
これらの措置なら、納税者自身が案件ごとに申告を行うため、
行政がすべての融資を監視する必要はなかった。
脱税意図のない納税者が自動的に取引を分類し、投機と実需が自然にふるい分けられただろう。
しかし政府は、こうした制度的に実現可能な方法をとらず、
バブルを経済全体のインフレと誤診した。
その結果、金融量を締める「総量規制」という最も粗い手段を選び、
局所的な熱を冷ますどころか、経済全体を冷凍させてしまった。
6. なぜ「悪い熱」だけを冷ますことができなかったのか
1980年代当時の行政制度や情報システムには、個別案件ごとに融資を選別する仕組みが存在しなかった。
銀行局(現・金融庁)はマクロ数量の監督はできても、案件の内容を識別するデータや権限を持っていなかった。
加えて「土地価格は下がらない」という土地神話が社会全体を支配し、
「土地融資=安全な融資」という前提が行政にも根強くあった。
そのため、大蔵省はもっとも即効性のある一律規制に踏み切り、
結果として健全な融資までも凍結してしまったのである。
7. r−g の再転換と「バランスシート不況」の始まり
金融引き締め後、名目金利は上昇したまま、成長率(g)は急落。
再び r−g>0 となり、債務比率は増加に転じた。
企業は債務削減を優先し、投資より返済を選ぶようになった。
この状態を、後にエコノミストのリチャード・クーが「バランスシート不況」と呼んだ。
民間部門が借金返済に集中するため、財政支出以外に有効需要が生まれない。
しかし、政府は依然として「財政均衡」を優先し、景気対策は限定的だった。
日本経済はこうして「第二の緊縮期」に入り、
金利上昇(r)と成長率低下(g)の組み合わせによって債務比率(d)は再び上昇。
企業・家計・政府すべての部門でデフレ的圧力が定常化した。
8. 政策思想としての「第二のドッジ・ライン」
1980年代後半から1990年代初頭の日本は、表面的には繁栄していたが、
政策思想の根底には依然として「過熱=危険」「引き締め=健全」という静的均衡思考が支配していた。
日銀は「金融の正常化」を名目に緩和から急速な利上げに踏み切り、
大蔵省は「融資抑制」を行政指導として実施した。
その結果、r<g が持続していれば債務比率が下がったはずの局面で、
あえて r>g に転換させ、経済成長のエンジンを止めてしまった。
これは構造的に見れば、戦後のドッジ・ラインと同型である。
すなわち、「通貨の安定を優先して実体経済を犠牲にする」という選択である。
9. 小結
1985〜1995年の日本経済は、
プラザ合意による円高不況 → 金融緩和、
不動産・株式市場の過熱 → 政府の誤診、
総量規制と急激な金融引き締め → 経済全体の冷却、
という三段階をたどった。
本来は、不動産・株式だけが上昇していた局地的な価格高騰に的を絞るべきだったが、
政府はこれを「経済全体のインフレ」と誤って判断した。
この認識の誤りが、総量規制という過剰反応を生み、
バブル崩壊を政策主導の墜落へと導いたのである。
次章では、この「緊縮と誤診の連鎖」が、1990年代後半以降どのように制度化され、
プライマリーバランス信仰へと結晶していったかを検証する。
第5章 デフレ期の財政錯覚――プライマリーバランス信仰の制度化(1997–2012)
1. 1997年という転換点:増税と緊縮の同時実施
1990年代半ば、日本はようやくバブル崩壊後の混乱から脱しつつあった。
しかし、1997年の橋本龍太郎内閣は、消費税率を3%から5%へ引き上げ、医療・年金の自己負担を増やし、特別減税を打ち切った。
この「財政再建三点セット」は、アジア通貨危機の発生と重なり、国内需要を急激に冷却させた。
実質成長率はマイナスに転じ、税収も大幅に減少。
同年に成立した財政構造改革法は歳出削減を制度化したが、景気悪化で早々に凍結された。
結果として、需要が落ち込む局面で緊縮が重なり、デフレ圧力が固定化された。
2. デフレの仕組み:r−g が正のまま固定
デフレ下では物価下落により実質金利(r)が上昇する。
一方で、需要不足により経済成長率(g)は低迷。
そのため、r−g は常に正(r>g)となり、債務対GDP比(d)は自然に上昇していく。
ドーマー条件
Δd=(r−g)×d
に従えば、r−gが正のままでは、PBを小幅に黒字化しても Δd(債務比率の変化) は下がりにくい。
つまり、「黒字化」では債務比率を下げられない構造的環境にあった。
3. PB信仰の制度化
1990年代後半、行財政改革と新自由主義的な経済政策が結びつき、
「財政再建=善」「赤字=悪」という道徳的フレームが再び強化された。
政府は1999年以降、プライマリーバランス(PB)黒字化目標を明示的な政策目標とし、
経済財政諮問会議や国際機関(IMF・OECD)もそれを支持した。
しかしこの時期、国際的にはすでにドーマー条件が債務分析の標準的枠組みとなっていた。
r<gであれば債務比率は自然に低下する――この原理は、
財務省・日銀の専門官僚も理解していた。
それでも日本政府は、「PB黒字化」を絶対目標として維持した。
つまり、理論を知らなかったのではなく、理論を知りながらも信仰を捨てられなかったのである。
この“PBドグマ”は、経済合理性ではなく制度文化として根付いた。
予算編成のKPI(Key Performance Indicator=主要業績評価指標)が「PB赤字の幅」に固定され、
成長率(g)や金利(r)といった動学的指標は議論の周縁に追いやられた。
4. 小渕・森・小泉の時代:拡張と緊縮の往復運動
小渕恵三政権(1998–2000):景気対策として公共投資・定額減税を実施、一時的に回復。
森喜朗政権(2000–2001):拡張と引き締めを行き来し、方向性が定まらず。
小泉純一郎政権(2001–2006):「構造改革なくして成長なし」を掲げ、不良債権処理と歳出削減を断行。
→ 成長よりもPB重視の方針を続け、デフレ下で実質金利(r)が相対的に高止まり。
見かけ上の金利は低かったが、物価下落のため実質r>gの関係が続き、
債務比率(d)は改善しなかった。
それでも「財政再建が進んでいる」という政治的演出が優先された。
5. 金融危機と民主党政権:危機対応後のPB回帰
2008年のリーマンショックに際して、麻生政権は大型の景気対策を実施した。
一時的に拡張政策が復活したが、危機が収束すると再びPB路線に回帰。
2009年の民主党政権(鳩山・菅・野田)は、財政健全化を主要公約とし、
2012年には消費増税法(5%→8%→10%)を成立させた。
需要が回復していない状況で増税方針を決定したことは、
期待形成を通じてデフレ圧力を強め、r−gを改善させる契機を失わせた。
6. なぜ失敗したか
誤ったKPI設定:
「PB黒字化」が目的化し、r−gの改善(成長>金利)が政策目標にならなかった。需給ギャップの軽視:
需要不足の下での増税・歳出削減は、成長率gをさらに押し下げる。デフレ下の実質金利効果:
名目ゼロでも、物価下落により実質rはプラスとなる。往復運動のコスト:
景気悪化→補正→緊縮の繰り返しで、乗数効果が途切れ、潜在成長率も低下した。
7. 取るべきだった政策
消費増税の延期または一時的な減税による可処分所得の維持。
中長期の公共投資(防災・社会インフラ更新・デジタル化)で内需を底支え。
研究開発減税・賃上げ支援で生産性向上と消費拡大を両立。
自動安定化装置の強化で、景気悪化時に自動的に財政が働く仕組みを拡充。
政策KPIの転換:「PB黒字化」ではなく、“r<gを維持する”ことを明示的に目標にする。
8. 小結
1997〜2012年の日本は、デフレ下でPB黒字化を目指すという構造的誤りを続けた。
国際的にはドーマー条件に基づく「成長による債務軽減」が定着していたにもかかわらず、
日本はそれを政策判断に反映させなかった。
結果として、r−gが正のまま固定され、債務比率dは上昇。
再建を目指すほど再建から遠ざかるという逆循環が常態化した。
この時代、日本の財政運営は「恐怖から信仰へ」、そして信仰の制度化へと進んだのである。
第6章 アベノミクスと「一時的な動的均衡」(2013–2020)
1. アベノミクスの登場――三本の矢
2012年末、第二次安倍晋三内閣が発足した。
前章まで続いた「デフレとPB信仰」に対し、安倍政権は明確に異なる経済哲学を掲げた。
それが、金融緩和・財政出動・成長戦略の「三本の矢」である。
第一の矢である大胆な金融緩和は、日銀の黒田東彦総裁のもとで実行された。
マネタリーベースを2年間で2倍に拡大し、長期金利をゼロ近傍まで引き下げる。
第二の矢の機動的な財政出動では、公共投資を拡大し、デフレ脱却を掲げた。
第三の矢、成長戦略は構造改革を目指したが、短期的には金融・財政の両輪が主軸となった。
2. r<g の回復――20年ぶりの「動的均衡」
2013年以降、実質成長率(g)はプラスに転じ、名目GDPも緩やかに拡大した。
同時に、日銀の量的緩和により長期金利(r)は0%近辺に低下。
結果として、約20年ぶりに r<g の状態が出現した。
ドーマー条件に照らせば、これは債務比率(d)を自然に安定させる条件である。
実際、2013〜2018年の債務対GDP比は横ばいで推移し、
日本経済は一時的に「動的均衡」を取り戻した。
この局面こそ、「成長が債務を軽くする」原理を実地で確認できた稀な時期だった。
3. しかし、PB黒字化目標は残った
ところが、財務省はアベノミクスの枠内でもプライマリーバランス黒字化目標を維持した。
安倍政権は2013年に「2020年度までのPB黒字化」を閣議決定し、
その後も折に触れて「財政健全化との両立」を強調した。
結果として、金融緩和と財政出動という拡張政策の裏で、
中期的には「均衡回帰」が制度的に仕込まれた。
つまり、短期的にr<gを作りながら、長期的にはr>gへ戻る構造を自ら設計していたのである。
PB黒字化というKPI(Key Performance Indicator=主要業績評価指標)は、
政治的には「責任ある財政運営」を示す指標として機能したが、
経済的には成長の持続を妨げる制約になった。
4. 消費増税とr−g の逆転
2014年、政府は消費税率を5%から8%へ引き上げた。
この増税は、PB黒字化目標を優先する財務省主導の政策であった。
直後にGDP成長率はマイナスへ転落し、個人消費が冷え込んだ。
その後、成長率(g)は低下し、r−gは再びゼロ近辺または正に転じた。
2019年にはさらに消費税10%が実施され、景気は再び減速。
ドーマー条件上、r−gがわずかでも正に転じると、
債務比率(d)は上昇方向に戻る。
こうして、一時的に実現したr<gは持続しなかった。
5. アベノミクスの成果と限界
アベノミクスは短期的には有効だった。
株価上昇・雇用改善・企業収益の拡大
名目GDPの拡大(約480兆円→550兆円)
インフレ率もプラス圏を維持(0〜1%台)
しかし、財政政策がPB制約に縛られ、
構造的な賃金上昇・需要拡大に結びつかなかった。
「金融緩和でrを下げる」ことには成功したが、
「財政政策でgを押し上げる」持続的メカニズムを作れなかった。
結果として、r<gを維持するには財政拡張が必要だったにもかかわらず、
政府はPB目標を優先して緊縮へと傾き、
「成長が債務を軽くする循環」を短命に終わらせた。
6. 政策思想としての「自己否定的均衡」
アベノミクス期の日本は、政策としてはr<gを目指しながら、
制度としてはPB黒字化というr>gを再生させる仕組みを同時に持っていた。
つまり、
成長を促す手でアクセルを踏みつつ、
財政規律という名のブレーキを常に踏んでいた。
これは「拡張政策と緊縮理念の共存」という矛盾であり、
結果的に持続的動的均衡(long-term r<g)の実現を阻んだ。
7. 小結
アベノミクスは、1990年代以降のデフレ局面で初めてr<gを実現し、
ドーマー条件に沿った「健全な財政動学」を再現した。
しかし、その成果を持続させる前に、
政府はPB黒字化目標という制度的ドグマを温存し、
再び「均衡」へと引き戻された。
この時期、日本は成長による財政再建の可能性を自ら手放したといえる。
第7章では、2020年以降のコロナ危機で一時的に封印されたPB信仰が、
どのようにして令和期の政策判断に再び影を落としたかを検証する。
第7章 コロナ危機と令和の転機(2020–現在)
1. パンデミックがもたらした“禁忌の解除”
2020年、新型コロナウイルス感染症が世界を襲った。
各国政府は、感染拡大を防ぎつつ経済を支えるため、かつてない規模の財政出動を決断した。
日本政府も例外ではなく、同年春に約120兆円の緊急経済対策を編成。
特別定額給付金、雇用調整助成金、持続化給付金など、
直接的な資金注入が国民経済の隅々にまで及んだ。
この時期、日本政府はプライマリーバランス(PB)目標を一時的に凍結した。
長年にわたって「赤字は悪」とされてきた財政運営に、
突如として「支出は正義」という逆転の論理が現れた。
結果として、2020〜2021年の日本経済は短期的にr<gの関係を回復。
金利(r)は歴史的低水準で安定し、経済成長率(g)は反動的にプラスを示した。
ドーマー条件に基づく自然な債務安定メカニズムが再び働いた時期である。
2. “特例国債”と国民の認識変化
政府は、補正予算の財源として特例国債を大量に発行した。
市場では国債金利が上昇するどころか、むしろ安定。
日銀の金融緩和が継続していたことに加え、
投資家が日本国債の信頼性を依然として高く評価していたためである。
この経験は、少なくとも一時的に、
「国債を増やせば金利が上がる」という従来の財務省的ドグマを否定した。
人々の間には、
「政府が本気を出せば、経済を支えることはできる」
という新しい現実感が芽生えた。
しかし、この“例外の成功”は、危機の終息とともに急速に忘れられていく。
3. PB信仰の再来
2022年、コロナ危機が落ち着くと、政府・財務省は再びPB黒字化目標を掲げた。
同年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、
「2025年度までのPB黒字化」を明記。
メディアも「異常な財政出動からの正常化」を肯定的に報じた。
しかし、デフレ的な構造は依然として解消していなかった。
人口減少と低賃金構造が内需を抑制し、
金利は低いまま、成長率(g)はそれをわずかに下回る水準に戻った。
再びr−gが正(r>g)となり、債務比率(d)は安定せず。
危機の教訓が制度に定着する前に、旧来の均衡ドグマが復活した。
4. 国際的潮流との乖離
同時期、欧米ではコロナ後の財政政策に明確な転換が見られた。
米国:バイデン政権が大規模財政支出(インフラ・気候投資)を継続。
欧州:財政規律条項(マーストリヒト基準)を一時停止し、成長優先を明言。
いずれも「成長が債務を軽くする」というドーマー的発想を前提にしていた。
対照的に日本は、危機が去ると同時に「財政の正常化」という言葉のもと、
再び赤字削減=善という戦後型の価値観へ回帰した。
5. 制度文化としての“PBドグマ”
ここに至ると、PB黒字化目標は単なる政策目標ではなく、
制度文化(Institutional Culture)として完全に定着している。
官僚の昇進や評価システム、政治家の説明責任、
そしてメディアの報道枠組みまでが「財政均衡=善」を前提に作動している。
この構造のもとでは、
どれほど経済理論が更新されようとも、
どれほどr<gが実証されようとも、
財政均衡の信仰は自動的に再生産される。
それはすでに政策ではなく、国家運営の宗教的前提に近い。
6. r<gを維持するという新しい規律
しかし、コロナ期の経験が示したように、
r<gを維持する政策運営こそが、真の財政健全化の条件である。
金利よりも成長率が高い状態を保つためには、
財政を“縮める”のではなく、“使い方を賢くする”必要がある。
教育・科学技術・防災・デジタル・再生エネルギーなど、
長期的リターンを生む支出に資金を振り向ける。逆に、非効率な補助金や短期的バラマキは削減。
「支出削減ではなく支出構造の転換」が新しい財政規律の形である。
この転換がなければ、日本は今後もr−g>0の定常デフレ構造に留まり続ける。
7. 小結――恐怖から整合へ
2020年代の日本は、戦後から続く「恐怖と均衡の連鎖」を断ち切る最後の機会を迎えている。
ドッジ・ライン以降:財政赤字への恐怖。
1990年代以降:PB黒字化という信仰。
コロナ期:一時的な恐怖の解除と成功。
コロナ後:信仰の復活。
この80年の歴史が示すのは、
制度が恐怖を再生産し、理論がそれを止められなかった国の姿である。
結論――「インフレ恐怖」と「均衡信仰」が経済厚生を蝕んだ八十年
戦後日本の財政運営は、常にインフレ(通貨価値の下落)への恐怖と財政均衡への信仰に支配されてきた。
1949年のドッジ・ライン以降、政府は一貫して物価安定を最優先とし、
財政の健全性を「赤字の有無」で測る静的な均衡観を制度化した。
経済が拡大するためには、短期的な赤字や公的投資が必要な局面もある。
しかし日本の政策当局は、「支出は不健全」「均衡こそ正義」という倫理的前提を優先し、
経済の実態よりも帳簿の整合性を重んじた。
その結果、財政政策はしばしばr−g(実質金利と経済成長率の差)の関係を無視して運営された。
理論的には、金利より成長率が高い(r<g)状態を維持すれば債務比率は自然に安定する。
これはドーマー条件が示す普遍的な原理であり、
国際的にも債務の持続可能性を判断する標準的な枠組みとなっている。
にもかかわらず、日本政府はこの理論を理解しながら採用しなかった。
代わりに、プライマリーバランス(PB)黒字化という単年度会計上の目標を最上位に置き、
「財政健全化=赤字削減」と短絡的に定義した。
これにより、r−gの改善(=成長による健全化)よりも、
歳出抑制と増税による帳簿上の黒字化が政策目的として固定された。
その結果、デフレ期には実質金利rが上昇し、成長率gが低迷。
r−gが正の状態が長期にわたり続いたことで、
債務比率は下がらず、家計所得や企業投資も伸びなかった。
つまり、財政健全化を掲げた政策が、国民経済の厚生をむしろ損なう結果を生んだのである。
恐怖から生まれた規律は、やがて思想となり、思想は制度へと転化した。
そして制度は、理論が誤りを示しても自らを修正できない構造を形成した。
これが、ドーマー条件に「見て見ぬふり」を続けた日本財政の実態である。
今後の財政運営が本当に健全なものとなるためには、
赤字や黒字といった静的な数値ではなく、
経済の成長と金利の関係(r−g)を基準に据える必要がある。
財政健全化とは、支出を減らすことではなく、
成長によって債務の重さを軽くする環境を維持することである。
理論に基づき、国民の厚生を目的として財政を運営する。
その転換こそが、戦後八十年に及ぶ「インフレ恐怖と均衡信仰」の時代を終わらせる唯一の道である。
当サイト内他の記事への移動は
▶ 当サイト内の全トピック一覧。最上位ページです。
当サイト内記事のトピック一覧ページ