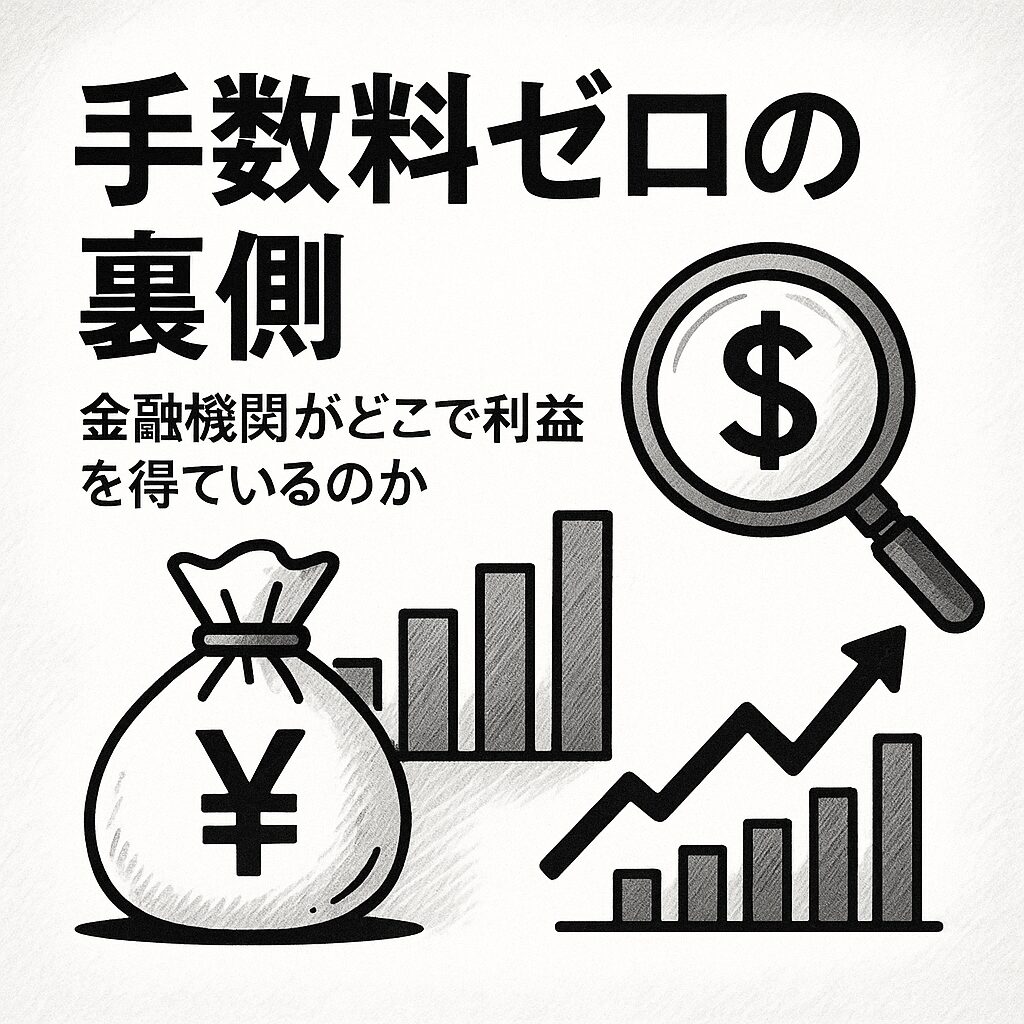Contents
■ はじめに
近年、多くの金融サービスが「手数料ゼロ」を掲げている。
株式売買の手数料ゼロ、FXの取引手数料ゼロ、投資信託の販売手数料ゼロ──。
しかし、手数料がゼロだからといって、
本当に金融機関が無料でサービスを提供しているわけではない。
金融機関は慈善団体ではなく、利益を追求する組織である。
そこで働く人がいて、システムを維持するコストもある。
つまり、
「タダで使えるはずがない」。
では、どこで利益を得ているのか。
この記事では、その構造を明らかにしていく。
■ 第1章 なぜ金融機関は手数料ゼロを掲げられるのか
金融機関にとって手数料ゼロは「入り口」である。
“無料”と聞くと安心する
手数料がないと、売買が積極的になる
商品選択のハードルが下がる
こうして投資家の行動を“促し”、
結果として金融機関の利益が増える仕組みが裏で動いている。
金融ビジネスは必ずどこかで利益を得る。
利益なしには、
サーバー
セキュリティ
システム開発
コールセンター
スタッフの給与
これらは維持できない。
**
「手数料ゼロ」は、“ただそう見せているだけ”なのだ。
■ 第2章 スプレッド──最もわかりやすい「隠れ手数料」
スプレッドとは、買値と売値の差のことである。
外貨両替がもっとも分かりやすい例だ。
1ドルを150円で「買える」
しかし売るときは148円
この 2円の差が金融機関の利益である。
実質的にはこれが「手数料」なのだ。
株式・FX・CFD・仮想通貨……
これらの世界でも、
スプレッドは常に存在し、しかも投資家が気づきにくい。
「無料」を掲げながら、
別の名目で確実に利益を取る仕組みがここにある。
■ 第3章 売買回数が増えるほど、不利になる構造
“手数料ゼロ”と聞いて安心し、
頻繁に売買を繰り返す投資家は多い。
しかし、売買回数が増えるほどスプレッド負担が累積し、
金融機関の利益が増える。
投資家は気づかないうちに
指数関数的に不利な状況に追い込まれていく。
これは個別株やFXで「動く」人ほど陥る典型的な罠だ。
■ 第4章 投資信託の裏側で動く“継続手数料”
投資信託は販売手数料ゼロ化が進んだが、
代わりに 信託報酬(運用管理費用) が金融機関の収益源になっている。
投資家が保有している間、
運用会社 → 証券会社へ“継続的に”手数料が流れ続ける。
つまり、
「買うときは無料です」
→ 「持っている間に利益をいただきます」
という構造だ。
■ 第5章 なぜ無料に見えるのか
金融機関が「手数料ゼロ」を多用するのは、
心理的な効果が大きいからだ。
無料 → 安心
手数料がない → 取引量が増える
宣伝として強い → 競争に勝てる
しかし実際には、
金融機関は必ず別の形で利益を得ている。
金融機関は悪ではない。
ただし、
構造を理解しない投資家は、常に不利な側に立たされやすい。
■ 第6章 利益の仕組みを理解すると、投資家は強くなる
重要なのは、「金融機関を敵視すること」ではない。
利益の仕組みを理解したうえで、適切な距離感を持つことだ。
無駄な売買を避けられる
スプレッド負担を減らせる
無料に過剰反応しなくなる
冷静な投資判断ができる
仕組みを理解することで、
資産形成における“構造的な不利”を大幅に減らせる。
■ 結び
金融機関は利益を追求し、
そのための仕組みを必ずどこかに持っている。
「手数料ゼロ」という言葉は、
その仕組みの一部を“見えなくしている”だけだ。
投資家に必要なのは、
無料の言葉を信じることではなく、
裏側の構造を読み解く眼である。
これさえ持っていれば、
不必要な取引に誘導されることもなく、
長期的な資産形成の基盤は、より強く、より揺らぎにくくなる。
当サイト内の他記事へは下記から
資産形成についての記事一覧
当サイト内記事のトピック一覧ページ 【最上位のページ】
筆者紹介は理屈コネ太郎の知ったか自慢|35歳で医師となり定年後は趣味と学びに邁進中