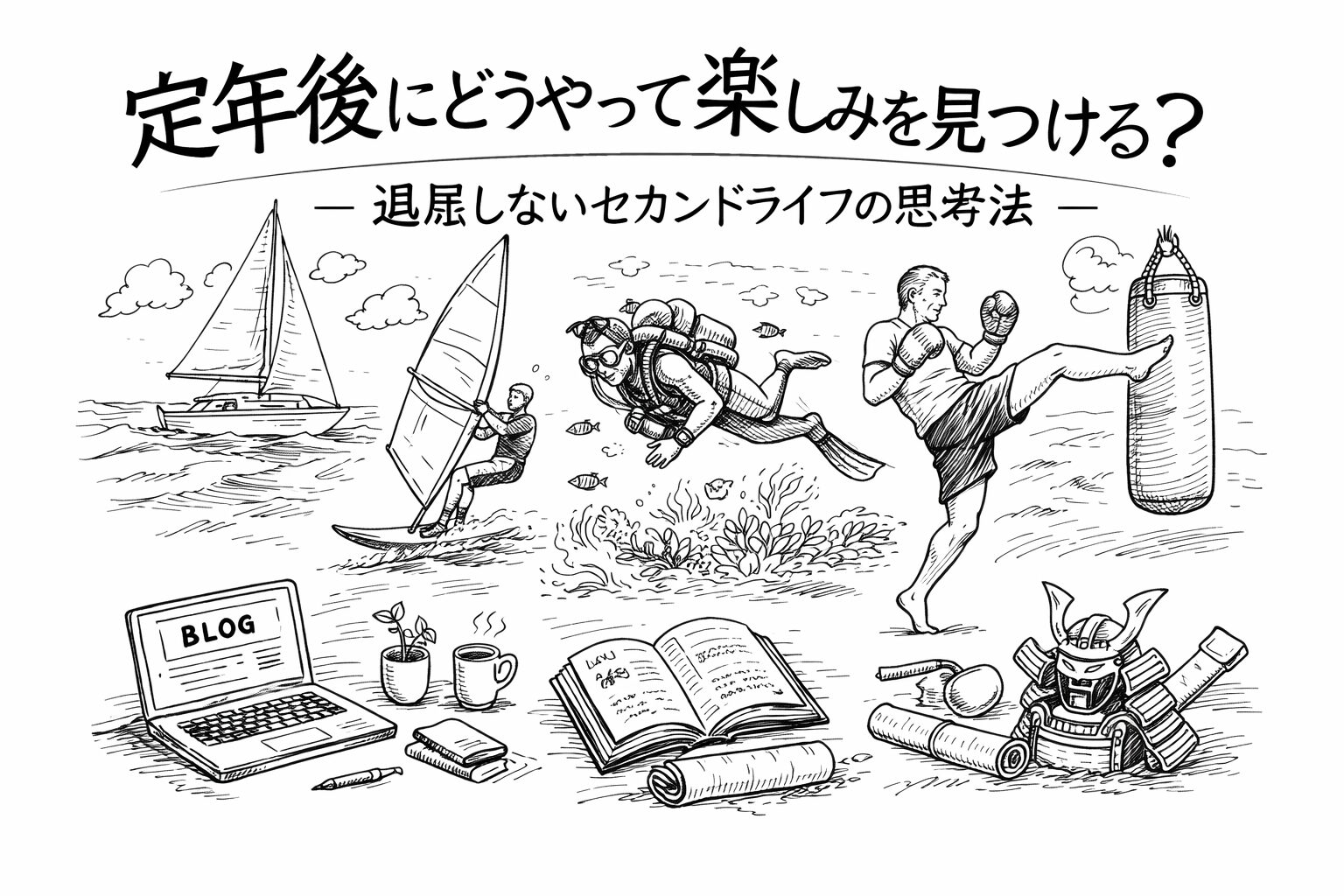Contents
はじめに|「考えて趣味を選ぶ」という矛盾
「定年後は何か趣味でも始めようと思う」
この言葉を、私は医師として受診者たちから何度となく聞いてきました。
けれども、その“考えて選んだ趣味”が長く続いた人を、ほとんど見たことがありません。
なぜなら、趣味とは本来、考えて選ぶものではなく、気づいたら夢中になっているものだからです。
考えて選んだ時点で、そこには「効率」や「意味づけ」や一種の「損得」が入り込み、趣味は“目的化された行為”へと変質してしまいます。また、趣味には人との相性があったりもします。相性のわるい遊びは趣味として長続きしません。詳細は別記事釣り・ゴルフ・将棋から考える偶然と必然──趣味の幸福論を参照して下さい。
第1章:趣味は「惹かれてしまう」ものである
本当の趣味は、ついつい自然に惹かれてしまう行為です。
その魅力は、簡単には言語化できません。
時間を忘れ、誰に褒められなくても続けてしまう──そこにこそ、趣味の本質があります。
逆に、「何か始めなきゃ」「健康に良さそうだから」といった理性的な動機で選んだ趣味は、ほとんどの場合、長く続きません。
それは“義務”としての行いであり、“喜び”としての趣味でないからでしょう。
趣味とは、面白そう、楽しそう、と気軽に始めたことが、なんとなく自然に継続してしまう行為です。。
たとえば子どもが泥遊びに没頭するように、理由も説明もないのが本来の姿。
理屈が先に立つと、その行為は“設計された余暇”になってしまいます。
関連記事➡覚醒するほど面白いシニア趣味12選|元医師が実体験で厳選!
第2章:受け取るだけの趣味は、やがて飽きる
とはいえ、趣味にはいくつかの段階があります。
最初は「受け取るだけ」で構いません。映画を観る、音楽を聴く、風景を眺める──いずれも素晴らしい時間です。
けれども、長く続けると、どこかで物足りなさが訪れます。
それは、人間の本能として、想いや思考の結果を何らかの形にしたいという欲求が芽生えるからです。
受け取るだけでは、感動が閉じたままになってしまう。
心の中で共鳴した何かを、外に出して初めて、趣味は“自分の表現”として一つの完結をみます。
写真を撮る、感想を書く、友人に語る、ブログに掲載する──形は何でもいいのです。
このアウトプットが始まったとき、趣味はようやく“生きた趣味”になります。
第3章:アウトプットが「自分だけの物語」をつくる
趣味を続けている人には、共通点があります。
それは、なんらかの方法で感動を自分の言葉で再構成しているということです。
釣りをする人なら戦略を語り、釣果や環境を他者と共有し、
写真を撮る人は作品を発表し、音楽を愛する人はその曲の背景を語る。
どれも単なる報告ではなく、自分の中で再体験し、意味づける作業です。
今はブログというツールがあるので、発表の場に困ることはありません。
この「アウトプットの過程」が、私たちに自己理解をもたらします。
そして、他者とのつながりも生まれる。
発信は必ずしもSNSである必要はありません。
ノートでも、日記でも、独り言でもよいのです。
言葉にすることで、趣味はあなたの中に「文脈」を持ちはじめます。
第4章:続く趣味と、続かない趣味の違い
続く趣味には、共通して“循環”があります。
インプットで得た感動を、アウトプットで再生する──この往復運動こそが継続のエネルギーです。
一方で、流行や効果を基準に始めた趣味は、外部の刺激が途切れた途端に冷めてしまいます。
つまり、趣味を育てるのは外の評価ではなく、自分の内側の温度です。
長く続ける人ほど、上手くなることを目的にしません。
むしろ「上手くならなくてもいい」と思った瞬間に、楽しさが増していくのです。
趣味は勝負の場ではなく、対話の場。
それは他人とのではなく、自分自身との静かな会話なのです。
結び|趣味は「見つける」ものではなく「育つ」もの
考えて選んだ趣味は、最初から“答え”を求めています。
しかし、趣味とは“問い”のほうに価値がある世界です。
「これが好きだ」と断言できるようになるまでには、何度も迷い、飽き、また戻ってくる過程が必要です。
そしてまた、他の趣味も幅広く体験してみることも大切です。
おもしろそうな事を色々なことを体験してみる。
やってみて、やめて、またやりたくなる──その往復を何度か経て、ようやくそれは“あなたの趣味”になる。
つまり、趣味は考えて始めるものではなく、いつのまにか生活の一部になるものです。
そして受け取るだけで終わらせず、何かしらの形でアウトプットすることで、
趣味の質と深さはますます磨きがかかります。
あなたの趣味は、時間を越えて成長しつづけるでしょう。