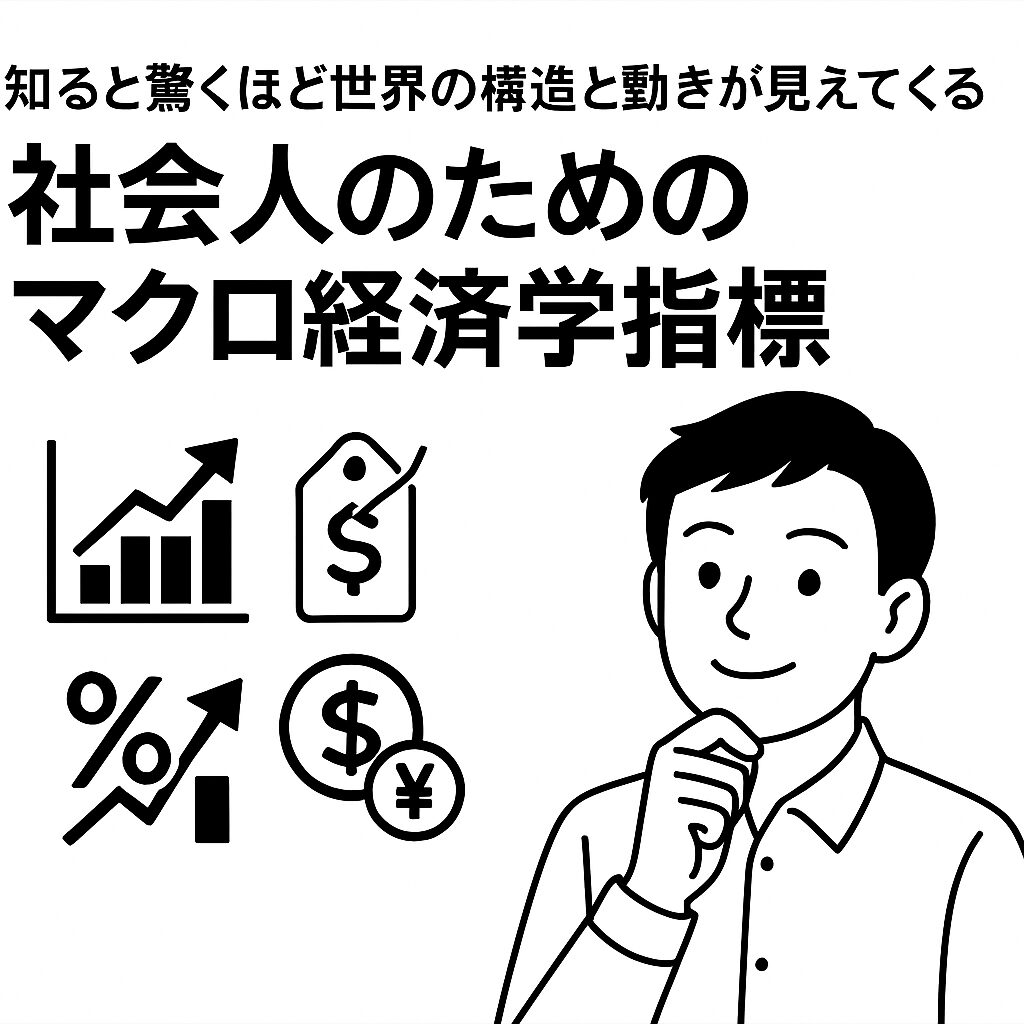Contents
■ はじめに
マクロ経済学は、高度で複雑な理論体系をもつ学問です。大学で深く学ぶには、数理モデルや統計学、金融論の知識が不可欠であり、決して簡単な学問ではありません。
しかし、そこから抽出される“エッセンス”――
すなわち 基本指標が何を意味し、どのように世界の動きを形づくっているのか という理解は、驚くほどシンプルで、そして驚くほど実用的です。
しかも、このエッセンスは、マクロ経済学そのものに興味がなくても役に立ちます。
むしろ、興味がなくても日常生活の意思決定に大きな恩恵をもたらす“実用の知恵”です。
本稿で扱う指標は、学者や専門家向けの知識ではなく、
社会人が自分の生活・将来設計・政策判断に活かすための最小限ツールセット です。
これらを知るだけで、
経済が今どの局面にあるのか
金利や為替がどう動くのか
政府の政策は整合的か
生活設計で何を優先すべきか
といった判断が、自分の頭でできるようになります。
そして何より、
これらの指標を知ると、世の中の構造と動きが驚くほどクリアに見え、
今後の生活設計のうえで確かな道標となる。
わたしはそう考えています。
関連記事➡経済政策と資産形成──「保留中の欲望」を動かす国は資産形成に優しい
関連記事➡マクロ経済学は社会人最強の武器|トラス政権と“誤診されたバブル”の教訓
■ 第1章 失業率──景気の“熱のセンサー”
● 失業率の定義
失業率とは、
働く意思があり、求職活動をしているが職がない人の割合
です。
つまり、
「働く気がない人」は含まれない
働き方(正社員・非正規)は無関係
求職活動をしているかどうかが鍵
という点がポイントです。
● 経済における意味
失業率は、景気を最も早く反映する指標のひとつです。
失業率が低い → 景気が加熱気味(労働力不足)
失業率が高い → 景気が冷えている(需要不足)
中央銀行は、利上げや利下げの判断を行うとき、必ず失業率を確認します。
景気の“温度”を見るのにこれほど直感的な指標はありません。
● 解釈のしかた
アメリカでは4%を切ると「過熱」
日本は構造的に低失業率なので、2.5〜3.0%でも「労働逼迫」
数字よりも 3ヶ月平均のトレンド が大事
■ 第2章 GDP成長率──“経済そのものの速度”
● GDPの定義
GDP(国内総生産)とは、
国内で新しく生み出された付加価値の合計
です。
種類は2つ:
名目GDP:物価変動込み
実質GDP:物価変動を除いた「生活水準の上昇」を示す指標
● 経済における意味
GDP成長率を読むことで、
景気が拡大中なのか
停滞しているのか
後退中なのか
が分かります。
GDPが伸びなければ、
給与は上がらず
企業利益も伸びず
税収も増えない
つまり、国全体の「生活水準」が停滞します。
● 解釈のしかた
四半期GDPの“年率換算”に注意(例:+0.3% → 年率+1.2%)
「前期比」と「前年同期比」は全く違う意味を持つ
2期連続マイナス=テクニカルリセッション
長期的には先進国で**1.5〜2.5%**が標準的成長
■ 第3章 インフレ率(CPI・コアCPI・コアコア)──通貨の“体温計”
● CPIの種類
インフレ率はCPI(消費者物価指数)で示されます。
CPI総合:生活実感に最も近い
コアCPI:食品を除いた物価指数
コアコアCPI:食品とエネルギーを除いた“基調インフレ”
● 経済における意味
インフレ率が高い → 通貨価値が下がる → 金利が上がる
インフレ率が低い → 需要不足 → 不況に陥りやすい
先進国が「2%程度のインフレ」を理想とするのは、
デフレ(物価下落)は給与の停滞を招く
適度なインフレは投資・生産を促す
ためです。
● 解釈のしかた
インフレは“上がるのは早く、下がるのは遅い”
コアコアCPIは中長期の物価動向を見るのに最適
インフレ率が高いと、中央銀行は利上げを行いやすい
■ 第4章 マネーサプライと金利──“血液”と“血圧”
● マネーサプライとは
マネーサプライ(M2)は、
社会に流通するお金の総量
です。
現代の通貨の9割以上は紙幣ではなく、
銀行の貸出の瞬間に帳簿上で生まれる「預金通貨」です。
(いわゆる信用創造)
● 金利との関係
金利は「お金のレンタル料」であり、
金利↑ → 借入が減り、マネーサプライの増加速度が落ちる
金利↓ → 借入が増え、マネーサプライが拡大する
金利は景気の アクセル(利下げ) と ブレーキ(利上げ) に相当します。
■ 第5章 為替相場──“国力”ではなく“通貨量の比率”で決まる
日本では、為替について次のような誤解がよく見られます。
「円安は国力が落ちたから」
「ドル高はアメリカが強いから」
しかしこれは、近代経済学から見ればほぼ誤りです。
● 為替の本質
為替は、
二国間のマネーサプライ(通貨量)と実質金利の差で殆ど決まる
という極めてシンプルな構造です。
通貨量が多い国 → 通貨価値は相対的に下がる
インフレ率が高い国 → 通貨が下がるのは当然
実質金利が高い国 → 通貨が買われやすい
つまり、
為替は国家の“国力”ではなく、金融政策の比較
によって決まります。
■ 結び
マクロ経済学の指標を知ることは、
経済ニュースを理解するためだけのものではありません。
今の景気局面
金利の方向
為替の裏の構造
インフレの持続性
政府の政策の妥当性
将来の生活設計(住宅ローンの金利をどう判断するかなど)
これらを“自分の頭で判断できるようになる”という、人生の武器になります。
マクロ経済学すべてを理解する必要はありません。
しかし、その エッセンス(指標の意味) だけでも、
あなたの世界認識は一変します。
ニュースが「騒音」から「情報」へと変わり、
未来に向けての判断が、驚くほどクリアになるはずです。
当サイト内の他記事へは下記から
資産形成についての記事一覧
当サイト内記事のトピック一覧ページ 【最上位のページ】
筆者紹介は理屈コネ太郎の知ったか自慢|35歳で医師となり定年後は趣味と学びに邁進中